日本は地震大国と言われていて、甚大な被害をもたらす巨大地震も多く発生しています。
最近起こった地震には、豊後水道を震源とする最大震度6弱、大隈半島東方沖を震源とする最大震度5弱、福島県沖を震源とする最大震度5弱などがあります。
その他にも、記憶に新しい石川県能登半島地震では、最大震度7を観測しました。
さらに遡っていくと、東日本大震災や岩手・宮城内陸地震、新潟県中越沖地震、新潟県中越地震なども記憶に新しいでしょう。
いずれも大きな被害が出ているので、万が一に備えた地震保険に加入するメリットは大きいと言えます。
Contents
地震保険とは?

地震保険は、地震や火山の噴火、それらが原因となって発生した津波で建物や家財が損害を受けた場合に補償する保険です。
建築技術が発達したことで、免震構造や耐震構造などの地震対策を施した物件も増えています。
一戸建てだけではなく、マンションやアパートといった賃貸物件でも同様です。
そのため、地震保険は必要ないと考える人もいるでしょう。
しかし、地震による揺れを軽減できたとしても、地震によって発生した火災で被害を受ける可能性もあります。
火災は火災保険で補償されますが、地震や噴火、それらによる津波が原因となって発生した火災・損壊・流失・埋没に関する保証を行わない保険商品が多くなっています。
地震はただ揺れるだけではなく、二次被害や三次被害を出す可能性があることを忘れてはいけません。
それを踏まえて考えてみると、地震保険には加入すべきだと言えるでしょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険と火災保険との違い

地震保険に加入する際、その補償内容や補償対象をきちんと把握しておかなければいけません。
続いては、混同されがちな地震保険と火災保険との違いについてみていきましょう。
保険料
火災保険の保険料は、保険会社が自由に設定できます。
そのため、契約を結ぶ保険会社によって差があります。
一方地震保険は、政府と民間の保険会社が共同運営しているので、保険料の設定方法は統一されているのです。
したがって、地震保険は火災保険のように保険会社ごとの保険料を比較検討する必要がないと言えます。
補償内容
火災保険の補償内容は、火災や自然災害などで何らかの損害を受けた建物や家財を保証するというものです。
それに対して地震保険は、前述したように地震や噴火、それらによる津波が原因となって生じた損害への補償を行っています。
これがこの2つの保険の大きな違いだと言えるでしょう。
保険の対象となるものにも違いがあります。
地震保険は、住居のみに使用される建物および併用住宅、家具や家電製品などの家財のみです。
一方火災保険の対象は幅広くなっています。
火災の他に、落雷や風災・雹(ひょう)災・雪災、建物の外部から物体の衝突、盗難なども対象になります。
所得控除の対象か否か
火災保険は、所得控除の対象外です。
しかし地震保険の場合は、所得控除の対象となっています。
かつて火災保険も対象となっていましたが、2006年に法改正が行われ、2007年からは廃止されています。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険料が決まる要素

地震保険料が決まる要素には、建物の構造や耐震性能、所在地、保険の契約期間が挙げられます。
続いては、地震保険料が決まる要素について詳しく解説していきます。
建物の構造
建物の構造は、柱の種類と耐火性能によって判定されます。
地震保険の構造は、「イ構造」と「ロ構造」に分けられています。
「イ構造」の方が、保険料は安いという特徴があるので、現在住んでいる建物はどちらに該当するか確認しておきましょう。
・イ構造
イ構造に該当するのは、コンクリート造やコンクリートブロック造、鉄骨造、耐火建築物、省令準耐火建物、準耐火建築物などです。
・ロ構造
ロ構造に該当するのは、木造などイ構造以外の建築物となっています。
木造の建物よりもコンクリート造や鉄骨造などの建築物の方が万が一の時に被害を抑えられるケースが多いため、保険料の設定が低めになっています。
建物の耐震性能
地震保険には建物の耐震性能に応じた割引制度があるので、条件を満たしていれば保険料を抑えることができます。
建物の耐震性能による割引率は以下のようになっています。
・免震建築物割引
対象となる建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」だった場合に適用となります。
割引率は50%です。
・耐震等級割引
対象となる建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」もしくは国土交通省が定めている「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合に適用となります。
割引率は、耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10%です。
・耐震診断割引
対象建物が地方公共団体等による耐震診断もしくは耐震改修を行った結果、改正建築基準法における耐震基準を満たしている場合に適用となります。
割引率は10%です。
・建築年割引
対象となる建物が1981年6月1日以降に新築された建物である場合に適用となります。
割引率は10%です。
これらの割引制度は重複して適用することはできません。
建物の所在地
地震や津波などの被害に遭うリスクは、エリアによって異なります。
そのため地震保険は、政府が発表している地震動予測地図をはじめとしたデータをもとに都道府県ごとに保険料率が定められているのです。
保険料率は以下のようになっています。
| イ構造 | ロ構造 | |
| 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・大分県 | 7,300円 | 11,200円 |
| 宮城県・福島県・山梨県・・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・愛媛県・香川県・宮崎県・沖縄県 | 11,600円 | 19,500円 |
| 茨城県・徳島県・高知県 | 23,000円 | 41,100円 |
| 埼玉県 | 26,500円 | 41,100円 |
| 千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 | 27,500円 | 41,100円 |
これは、保険金額1,000万円あたりの地震保険料です。
1年ごとにかかる金額になります。
太平洋側にある都道府県は、地震保険料率が高い傾向があることがわかるでしょう。
契約期間
地震保険の契約期間は最長5年です。
契約期間を2年以上にすると、保険料を計算する際に長期係数が適用となり、割引を受けられるのです。
保険期間に応じた長期係数は以下のようになっています。
| 保険の契約期間 | 長期係数 |
| 2年 | 1.9 |
| 3年 | 2.85 |
| 4年 | 3.75 |
| 5年 | 4.7 |
契約の期間が長くなるほど、割引率が高くなり、支払うべき保険料の負担が軽減します。
2022年10月の地震保険改定により、5年契約の長期係数は4.65から4.7に見直しされました。
また、支払い方法を月払いや年払いではなく、一括払いにするとさらにお得になります。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
賃貸暮らしでも地震保険に加入するべき?

賃貸物件に暮らしている場合でも地震保険に加入した方がいいのか迷うケースも多いです。
続いては、賃貸暮らしでも地震保険に加入するべきなのか、という疑問に答えていきます。
日本は地震が多く発生する
冒頭でも述べたように日本は地震大国です。
いつどこで巨大地震が起こるかわかりません。
そのため、今のうちに備えておくことは重要です。
最大震度5以上の地震が発生した場合、建物が全壊や半壊となってしまう可能性が非常に高いです。
一部破損と判断されるケースも多いので、万が一に備えて保険に入っておく価値は大いにあります。
地震が起こった時に賃貸物件だから壊れないという保証はありません。
大きな地震が発生する頻度も高くなっているので、被害に遭う前にできることはやっておくべきだと言えるでしょう。
家財の修理や購入費用が高額になる
地震による被害を受けた場合、家財の修理や購入費用は高額になります。
東日本大震災で被災者生活再建支援制度を申請した人のおよそ半数は、家具や家電、寝具などの購入費用として50万円以上かけていました。
被災時にそれほどの出費が生じるのは大きな痛手になってしまうので、地震保険に加入して備えておくメリットは大きいです。
現在の物件に住めなくなった場合、多くの費用がかかる
地震による被害を受けた場合、賃貸物件に住み続けることができなくなることも考えられます。
そうなると、家財の修理や購入にお金がかかるだけではなく、引っ越し費用や新居を借りるための費用なども必要になります。
また、新居が見つかるまでのホテル代もかかってくるため、出費はかなり大きくなってしまうでしょう。
それらの費用を全て自己資金でまかなうには、資金的な余裕が必要です。
資金に余裕がない場合は、地震保険に加入し、万が一に備えておくべきだと言えます。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険料を支払っている場合、控除を受けられる

地震保険料を支払っている場合、所得控除を受けることができます。
次は、地震保険料控除の条件や控除額、申請方法についてみていきましょう。
地震保険料控除の条件
地震保険料控除の対象になるのは、保険契約者自身や保険契約者と生計を共にしている配偶者、その他の親族が所有する建物または家財が保険の対象になる地震保険契約です。
建物の用途にも注意が必要です。
地震保険料工事を受けられる建物は、居住用の建物だけとなっています。
普段から住居として使っていない別荘や空き家は対象外です。
住居の一部を事務所や店舗として使っている店舗併用住宅の場合は、居住用資産に係るものだけ控除の対象になります。
ただし、店舗併用住宅などでも、住居として使っている面積が全体の90%以上であれば、地震保険料全額を控除できます。
控除額について
地震保険料控除の控除額は、所得税と住民税で異なります。
それぞれの控除額についても確認しておきましょう。
【所得控除】
所得控除は、50,000円が基準となっています。
・その年に払った地震保険料が50,000円以下の場合…支払った保険料の全額
・その年に払った地震保険料が50,000円を超えている場合…一律50,000円
| 区分 | 年間支払保険料 | 控除額 |
| 1.地震保険料 | 50,000円以下 | 年間支払保険料の全額 |
| 50,000円超え | 一律50,000円 | |
| 2.旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 年間支払保険料の全額 |
| 10,000円~20,000円以下 | 年間支払保険料×1/2+5,000円 | |
| 20,000円超え | 一律15,000円 | |
| 1と2が両方ある場合 | 1と2の控除額の合計が50,000円以下 | 1と2の合計 |
| 1と2の控除額の合計が50,000円超え | 一律50,000円 |
【住民税】
住民税の控除額は、以下のように所得税と異なります。
・その年に払った地震保険料が50,000円以下の場合…支払った保険料の1/2
・その年に払った地震保険料が50,000円を超えている場合…一律25,000円
| 区分 | 年間支払保険料 | 控除額 |
| 1.地震保険料 | 50,000円以下 | 年間支払保険料×1/2 |
| 50,000円超え | 一律25,000円 | |
| 2.旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 年間支払保険料の全額 |
| 5,000円~1,000円以下 | 年間支払保険料×1/2+2,500円 | |
| 15,000円超え | 一律10,000円 | |
| 1と2が両方ある場合 | 1と2の控除額の合計が25,000円以下 | 1と2の合計 |
| 1と2の控除額の合計が25,000円超え | 一律25,000円 |
【旧長期損害保険料とは?】
旧長期損害保険料は、経過措置の対象になる保険です。
以下の条件に該当する場合、経過措置の対象になります。
・2006年12月31日までに締結した契約(保険期間もしくは共済期間の始期が2007年年1月1日以後のものは除く)であること
・満期返戻金のあるもので保険期間もしくは共済期間が10年以上になっていること
・2007年1月1日以後にその損害保険契約などの変更を行っていない保険であること
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の双方に該当している場合は、いずれかを選択できます。
その選択は年ごとにできるようになっています。
複数の契約があって合算するのであれば、控除限度額は50,000円(住民税の場合だと25,000円)になることも覚えておきましょう。
年末調整で申請可能
会社員などの給与所得者の場合、年末調整で控除の申請ができます。
年末調整を行う場合は、地震保険料控除照明書を勤務先に提出しなければいけません。
この書類は、加入している保険会社から10月くらいに送られてきます。
2020年10月分以降に関しては、年末調整の電子化が対応されている勤務先もあります。
そのような場合は、電子データのまま提出しても問題ありません。
ただ地震保険料控除照明書を職場に提出するだけではなく、年末調整書類の地震保険料控除の部分に記入することも忘れないようにしてください。
会社経営者や自営業、住宅ローン控除を受ける方などは確定申告が必要です。
申告の内容によって記載方法が異なる場合があるため、不安な場合場最寄りの税務署に問い合わせるのがおすすめです。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険請求の流れ

大切にしている家財が多くあったり、買い替え資金を持っていなかったりする場合は、地震保険への加入で助けられることも多いでしょう。
日本は地震大国なので地震保険の大切さを知っている方もいますが、もし地震保険に加入していた場合、どのようなタイミングで保険金を請求すべきかわからない方もいるでしょう。
ここでは、地震保険請求の流れについてご紹介します。
損害部分や状況の確認
地震保険を請求する場合、地震でどのような被害を受けたのかが重要です。
そのため、損害を受けた内容を確認しましょう。
建物や家財をできる限り確認し、どこにどのような被害が出ているかを把握してください。
地震の規模や状態によって確認が困難なケースもあるので、詳しい損害状態が確認できなくても問題ありません。
建物の倒壊などの二次被害を受けないように、十分に安全確認をしてから状況確認をしましょう。
損害状況を確認する前には、損害部分や片付けていない写真を残しておくと安心です。
地震で被害に遭った部分や物などを片付けてから写真を納めても被害状況が伝わりにくいです。
被害を受けた建物の損害部分、損害を受けた家財などがある場合は、様々な角度から写真を撮って残しておきましょう。
写真を残しておくことで家財の被害状況を知れるだけでなく、損害の全容が把握しやすいでしょう。
保険会社へ連絡する
損害が確認できた場合、加入している保険会社へ連絡します。
いつの地震でどのような損害が起こったのかを伝えますが、地震が大きい規模で起こった場合は保険会社の対応も遅れる可能性が高いです。
大手保険会社であれば、電話以外にもインターネットで連絡できる可能性が高いです。
電話が繋がりにくい場合は、ウェブから申請書の提出を行いましょう。
電話で連絡する場合は契約者氏名、被害の日時や状況、契約番号、連絡先などを伝えましょう。
保険金の請求は3年以内とされています。
これは、保険法によって定められているものであり、地震などの災害が起こってから時間だけが経過すると、被害状況の判断や把握、適正な評価などが困難になるからです。
申請期間が過ぎないように連絡しましょう。
訪問での状況確認
被害に遭って保険会社に連絡すると、保険会社から委託された鑑定人が訪問してきます。
鑑定人が訪問する際は立会人が必要なので覚えておきましょう。
多くの保険会社で、訪問までに1週間程度経過するのが定番なので、できる限り予定を合わせて参加してみましょう。
できるだけ、地震の被害に遭った時とその後をスムーズにするために、地震によって発生した損害を詳しく説明できるようにしてください。
被害を確認した状態で、メモを残しておくと伝え忘れが起こりにくいです。
他にも、現地調査が行われるのと同時に必要書類の作成がされることもあります。
現地調査の場合、地震で起こった被害であることを説明できる存在が必要です。
地震で起こった部分はどこか、経年劣化ではないことなどがクリアにできない場合は保険適応外になってしまいます。
現地での調査でおおよその保険金額も算出できるので、損害状況がどのようになっているかを確認できるように準備しましょう。
保険料の算定と確認
地震調査が終了すると、保険会社は保険金請求や現地詳細などで判断した情報から保険金額を連絡します。
この時に、判定区分となる「全損」「大半損」「小半損」「一部損」なども同時に伝えられます。
保険金の割合については以下のとおりです。
【保険金の割合】
・全損:地震保険金額の100%
・大半損:地震保険金額の60%
・小半損:地震保険金額の30%
・一部損:地震保険金額の5%
この区分は、保険金額の判定で問題がなければ承諾できるものです。
もし、提示された区分に納得できない場合は、確認不足や見落としと感じる損害部分を提示して具体的な証拠と一緒に損害保障会社に連絡しましょう。
納得できれば保険金の請求となり、発生した日の翌日から3年間です。
それ以上は効率上時効にかかるので早めにしましょう。
保険金支払い
保険金は、必要な書類と請求書を提出した日から原則30日以内に支払われることが多いです。
大規模な災害の場合は、これ以上日にちがかかるケースもあるので覚えておきましょう。
手順としては、現地調査で状況確認後に保険金が支払われます。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険金を請求する際のポイント

では、地震保険を請求する際にはどのような点が重要になるのでしょうか?
ここでは、ポイントに注目してみましょう。
地震保険の内容
地震保険は、火災保険の金額のうち30%~50%の間であることが条件です。
建物には5,000万円、家財には1、000万円を上限にしています。
「保険をかけているのに全額補償してもらえないのか」とがっかりするかもしれません。
しかし、この保険の意図は被災者の生活を安定させるものです。
生活の安定を守ることがメインなので、建物を立て直したり失った家財全てを購入する金額を補償したりするものではないと覚えておきましょう。
損害の大きさで保険金額が変わってくる
保険金額は、全額、大反損、小半損、一部損に分かれていて、損害の大きさによってこれらの分類が変わってきます。
| 区分 | 年間支払保険料 | 控除額 |
| 1.地震保険料 | 50,000円以下 | 年間支払保険料×1/2 |
| 50,000円超え | 一律25,000円 | |
| 2.旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 年間支払保険料の全額 |
| 5,000円~1,000円以下 | 年間支払保険料×1/2+2,500円 | |
| 15,000円超え | 一律10,000円 | |
| 1と2が両方ある場合 | 1と2の控除額の合計が25,000円以下 | 1と2の合計 |
| 1と2の控除額の合計が25,000円超え | 一律25,000円 |
請求する際には、このような条件に該当したものが支払われることを知っておきましょう。
また被害に遭ってから3年以内に請求することを忘れないようにしてください。
家財の写真は残しておく
自宅の家財の状態を見て、思わず片付けたくなるかもしれません。
しかし、一切手を付けない状態で写真を撮って保存してください。
これは、保険金請求時に必要となる証拠写真だからです。
家財が地震によって損害を受けたという証拠となります。
慌ててしまうと、写真を撮ることを忘れて元の状態に戻しがちですが、壊れた写真があれば災害で破損したことが認められます。
勝手に分解や処分しないようにする
保険金請求の際には、保険金の査定が終わるまでは勝手に家財を処分したり分解したりしないようにしましょう。
調査員が自宅に訪問して家財の破損状態を確認するケースがあります。
そのため、損害が出た家財に関してはそのまま破棄することなく、家に残しておきましょう。
そして、調査員が訪れた際には家財が壊れた写真と実際に壊れている家財の両方を見せる必要があります。
査定に不満があれば相談する
地震保険金を請求する際のポイントとして、査定に不満や納得できない部分があれば相談するという点です。
調査員が実際に現場に訪れて査定をしますが、その結果家財が明らかに壊れているのに損壊なしにされてしまった、きちんと査定してもらえなかったという場合もあるでしょう。
納得できないという点があれば、相談して再度査定をやり直してもらえるように伝えてみてください。
それでも結果に納得できない場合は、日本損害保険協会運営の「そんぽADRセンター」へ相談もできます。
そんぽADRセンターは、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情を受けたり、損害保険会社との紛争解決支援をしたりする機関です。
査定に疑問や不満がある時は、相談できることを知っておくと安心でしょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険に加入するための火災保険の選び方
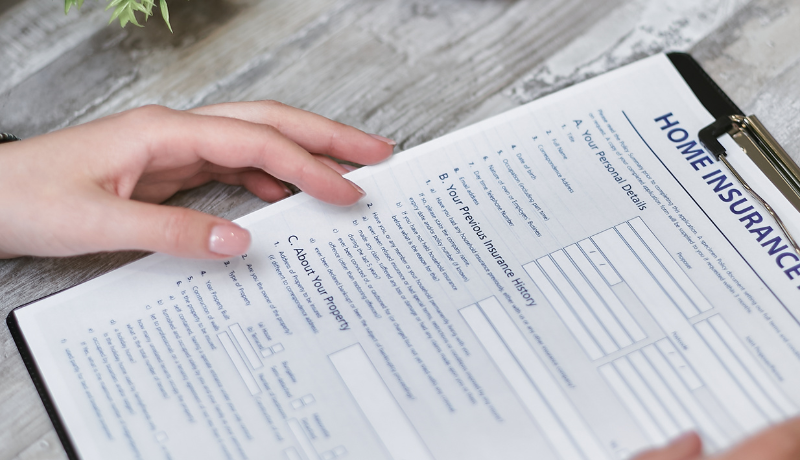
現在、保険には様々な種類や保証内容があり、地震保険といっても何を基準に選ぶべきか迷うことも多いでしょう。
ここでは、地震保険に加入するための火災保険の選び方についてみていきましょう。
地震保険を付帯する
まず、地震に対しての保障が欲しい場合は地震保険を付帯しましょう。
火災保険に入れば地震も補償されると思われがちですが、地震保険は単体での取り扱いがありません。
地震まで補償して欲しい場合は、火災保険に加入する際に地震保険を付帯することが必要になります。
地震保険は民間の保険会社と政府との間で運営されているもので、どこの保険会社で加入しても大きな差がありません。
そもそも、地震保険は巨大地震が起こった時に多額の保険金が保険会社だけではまかなえないことから共同の運営になっているのです。
そのため、火災保険加入時に地震保険を付帯することで加入できる仕組みとなります。
補償範囲を確認する
地震保険に加入する際には、補償範囲についても知っておきましょう。
先ほども紹介したように、国と保険会社の共同運営なのでどこに入っても補償内容は同じです。
ただし、火災保険の補償範囲に関しては、それぞれの保険会社によって補償範囲が異なります。
賃貸物件の場合は、水漏れなどのトラブルが多いです。
賃貸物件に適した補償があるか確認してみましょう。
建物の評価額に応じたものを選ぶ
保険は、契約時に決められた保険金額が上限になります。
保険金額が大きく、高い保険料を支払ったとしても、実際には損害額以上の金額を補償することはありません。
そのため、建物の評価額に沿った保険金額を選ぶことで適切な保険金額がわかります。
火災保険を契約する際には、建物の評価額や家財などに応じた金額で適切な保険料を決めてみましょう。
保険料を考慮し、保険期間と支払い方法を考える
火災保険は長期間の契約が可能であり、保険料は月払い、年払いなどから選択可能です。
長期契約して、保険料を一括支払いすることで料金を抑えて支払いが可能です。
実質的に火災保険の値上げが行われた場合は、長期の一括払いが最もお得になるでしょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
地震保険の加入で注意すること

「重要な家財はない」と地震保険に加入しないことを選択する方もいれば「何が起こるかわからない」と積極的に地震保険に加入する方もいるでしょう。
ここでは、地震保険の加入で気を付けたいポイントをご紹介します。
使うと次回補償が変わる可能性がある
地震保険料は、何度利用しても上がることはありません。
ただし、変わらないのは料金の話であり、補償内容ではありません。
例えば、72時間以内に震度6や震度7クラスの地震が起こったと仮定します。
大きな地震の後に余震が何度も来ますが、最初の地震から72時間以内に起こった地震は規模が大きくても1回の損害としてカウントします。
そのため、毎回被害を数えるのではなく、72時間で一区切りと考えるようにしましょう。
保険金の支払いは解約にならない
損害が認定されて、地震保険金額と同額の保険金の支払いがされると地震保険契約が終了します。
ただし、これは全損の場合のみです。
これについては、倒壊した建物自体がその場にあるものの、全壊したことで契約した建物がなくなっている状態だと判断されるからです。
再度建物を新しく建築した場合は、改めて地震保険への加入が必要です。
これ以外の認定であれば、保険金額が減少せずに契約継続となります。
修繕については、1回目で損害を受けて修繕した場合、受けた被害を元通りに修繕していることになっているので、再度同じ部分で損害が認定されれば保険金を受け取れます。
地震保険で全損認定されにくい
地震によって起こった災害では、一部損に認定されるケースが多くなっています。
過去にあった東日本大震災で支払われた保険金のデータを見ると、建物では54.6%、家財では16.2%が一部損と認定されました。
一方で全壊と認定された建物は3.3%、家財は1.6%と、評価が低いことが挙げられます。
この結果だけをみると、地震保険だけで災害時の補償をまかなうのはとても難しいでしょう。
ここまで、地震保険はどのような保険なのか、火災保険との違いや補償内容、仕組みや加入による注意点などをご紹介しました。
地震保険は単体でも加入ができず、火災保険に付帯する形となります。
政府が取り組んでいる保険で、いざという時に困らないようにするためにも必要な保険ですう。
この機会に地震保険について知り、今後加入も検討してみてください。
