不動産を売ったり、買ったりする際には不動産売買契約が発生します。
不要な土地や建物を売りたい、または新しい不動産を購入したいのであれば、不動産売買契約について正しい知識を身に付けることが大切です。
知識が不足したまま不動産売買を行うと、あとで後悔してしまう可能性があります。
そこで今回は、不動産売買契約の基本知識や注意点などをわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
Contents
不動産売買契約とは?

不動産売買契約は、不動産の売買が行われる際、契約内容に売主と買主の双方が合意することで締結される契約です。
一度契約すると簡単に取り消しはできないため、不動産売買契約について十分な理解が必要です。
まずは、不動産売買契約にはどのような特徴があるかご紹介します。
契約内容は自由に決めることが可能
売主と買主の間で交わされる不動産売買契約の内容は、自由に決めることが可能です。
ただし、法令違反や公序良俗に反する内容などは避け、常識的な契約内容にする必要があります。
しかし、契約内容を自由に決められる性質から、不動産売買契約は自己責任で締結するものだと理解しなければなりません。
特に重要な項目で不明瞭な契約条件となっていると、契約後にトラブルが発生するリスクがあります。
また、契約で定めがない項目は、民法や関連法令に基づいて協議して、契約条件を決めて同意を得なければなりません。
不動産会社が売主のケースでは契約内容に制限がかかる
不動産売買は個人間で行われるケースもあれば、宅地物件取引ができる不動産会社、その他事業者と行われるケースがあります。
売主が不動産会社であった場合、宅地建物取引業法に基づいて契約内容の一部に制限が設けられます。
制限を設けることで、買主にとって不利な契約で結ばれることを防いでいるのです。
消費者契約法が適用される
事業者と消費者の間で取引が行われる場合、消費者の保護を目的にした消費者契約法が適用されます。
消費者が契約内容を誤認して契約を締結したり、消費者に不利益な項目があったりした際に、契約の取り消しや無効化など消費者保護に関するルールが定められた法律です。
この法律は不動産売買においても適用されます。
なお、消費者契約法の保護対象は事業以外の目的で個人が契約を締結した場合であるため、たとえ個人でも事業を目的に契約を締結した際は保護の対象になりません。

INA&Associates Inc.は、不動産、IT、投資などにおける専門性と技術を活かし、高級賃貸・売買・事業用不動産仲介を中心とする総合不動産会社です。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫の賃貸管理、賃貸売買仲介、事業用不動産仲介・買取をメイン事業として展開しており、土地、マンションの有効活用の企画・提案、外資系法人の転勤者向けの社宅仲介も行っております。
契約解除や損害賠償請求にもつながる「契約不適合責任」とは?

不動産売買契約を交わす際、売主は契約不適合責任を負わなければなりません。
契約解除や損害賠償請求にも関わってくるので、売主も買主も契約不適合責任について理解を深めましょう。
契約内容が適合しない際に負う責任
契約不適合責任とは、不動産の売買が成立した後に、契約内容と実際の取引が適合しなかった際に売主が負う責任です。
不動産の売買では、売主は契約書に記された物件の種類・品質・数量に適合した物件を引き渡さなければなりません。
しかし、契約内容とは異なる物件を引き渡すとなると、契約義務を果たさなかったことになります。
購入した物件が契約内容と異なれば、買主は売主に対して補修を請求できます。
補修請求に対応してもらえなかった際は、売買代金の減額や損害賠償、契約解除を要求することも可能です。
ただし、損害賠償は売主に責任があった場合に限り請求できます。
また、契約解除に関しては、軽微な不適合であれば解除要求はできないので注意してください。
契約不適合責任の期間
民法では、不適合の事実が発覚してから1年以内に申し出ることで、売主は契約不適合責任を負うことになるとされています。
つまり売買から数年経っても、買主が契約不適合だと気付いた時点で売主に対して補修や損害賠償の請求が可能です。
しかし、引き渡しから長い年月が経っていると、元々あった欠陥なのか、経年劣化で起きたものなのか判断しづらくなってしまいます。
そのため、一般的に個人間での契約では、契約不適合責任を負う期間は不動産の引き渡しから2~3ヶ月とすることが多いです。
また、売主が不動産会社であった場合、契約不適合の通知期間は引き渡しから最低でも2年以上にすることが宅地建物取引業法で定められています。
不動産売買契約で特約が設けられることがある
上記で述べたように、不動産の欠陥は経年劣化や自然損耗によるケースもあり、契約不適合かどうか正確に判断できないケースがあります。
売主に対して不当な請求が行われるのを防ぐために、一般の不動産売買では特約を設け、責任を負う範囲や期間を限定することが可能です。
また、売主が一切責任を負わないという特約を付けることもできます。
ただし、そうなると買主は損をすることになるので、契約前に特約の内容をよく確認しましょう。
売主が不動産会社の場合も特約が有効となりますが、請求できるものが補修に限る、売主が認めた場合に契約解除が可能など、買主にとって不利な特約は適用されません。
さらに、不動産会社以外の事業者が売主となる場合、個人の取引のように売主が契約不適合責任を負わないという特約を設けることはできません。

Webサイトやオウンドメディアは、企業の想いや価値観を社会に伝える重要な手段です。
専門担当者の不足、ノウハウの不足、コストの不安などの理由で後回しになっていませんか?
私たちは、「人間的想像力 × テクノロジー」を最大限に活用し、企業が持つ本来の魅力を明確に可視化。社会から正当に評価される状態へと導きます。
不動産売買契約書でチェックすべきポイント

不動産売買契約は自己責任で行われるものであるため、買主は契約書の内容を入念にチェックすることが大切です。
そして、契約内容でわからないことは売主にしっかり確認を取り、疑問を解消した上で契約を締結しましょう。
ここで、契約書でチェックするべきポイントをご紹介します。
売買する不動産の表示内容
不動産売買契約の締結は、対象の不動産の情報が明確になっていることが前提です。
基本的に契約書には不動産登記簿に基づいた内容が記載されているので、取引する不動産の表示に間違いがないかチェックしてください。
売買代金や手付金の金額・支払日
売買代金と手付金の金額と支払日が契約書に記載されているか確認してください。
特に手付金に関しては、どういう目的の手付金なのか、妥当な金額なのかチェックしましょう。
手付金の種類や相場については、下記で詳しく紹介します。
土地の実測・土地代の精算
売主によって土地の実測が行われるのかどうか、契約書の内容から確認してください。
実際に測った土地の面積が、登記簿の内容と異なるケースがあるため、売主によっては引き渡し前に実測するケースがあります。
登記簿の内容と実測値に大きな差が生じている際は、売買代金の精算が行われることもあります。
実測するだけで精算は行われないこともあるので、土地代の精算が行われるかどうかもチェックしましょう。
所有権の移転と引き渡し時期
不動産の取引では、代金を支払った場で買主に所有権の移転登記で必要となる書類や鍵が渡されることが多いです。
しかし、引っ越しの予定日よりも大幅に早く引き取ってしまうと、余計な維持費がかかってしまう可能性があるでしょう。
引っ越しの予定を確認した上で、所有権の移転と引き渡し時期が無理のないタイミングになっているかチェックしてください。
付帯設備等の引き継ぎ内容
中古住宅の場合、照明やエアコンといった住宅設備や庭木・庭石なども引き継ぐことがあります。
付帯設備等の引き継ぎではトラブルが起きやすいため、何を引き継ぎ、何が撤去されるのか契約書をよく確認し、売主と買主の間で調整することが大切です。
また、引き継ぐ付帯設備に不具合や破損がないか、状態についても確認を取ってください。
負担の消除
負担の消除とは、売主が買主に対して取引する物件を完全な所有権で引き渡すために、「所有権の行使を阻害する負担を消除する」ことを示します。
簡単に言えば、抵当権や賃借権などの権利が売主によって完全に抹消された状態で、買い手に渡ることを約束する文言です。
抵当権や賃借権などが整理されていない場合、契約どおりに引き渡しが行われない可能性があるので、負担の消除の文言や権利が整理されているか確認しましょう。
投資用物件の売買では、テナントとの賃貸借契約に限り、買主が権利を引き継ぐことができます。
そのため、引き継ぐかどうかの権利を事前に明らかにする必要があります。
公租公課等の精算
公租公課(固定資産税や都市計画税など)は、売主と買主の間で精算するケースがほとんどです。
また、管理費やその他の諸費用を精算することもあるので、その内容をよく確認しましょう。
なお、清算は引き渡しから日割りで行われるのが一般的です。
手付解除の内容
やむを得ない事情から手付解約するケースがあるので、その取り決めを確認してください。
一般的には、手付解除できる期間を定めていることが多いので、その期間をチェックしましょう。
手付解除に関しては、双方の合意があれば手付解除を認めない契約条件にすることも可能です。
引き渡しまでの危険負担
売買契約を締結した後に、天災により建物が滅失・毀損することがあります。
この場合、売主と買主のどちらにも責任がないため、双方に負担が生じることになります。
そこで、契約書にはそのような事態に陥った時の取り決めが記載されています。
通常は売主が物件を修復して引き渡すことになりますが、修復に大きなコストがかかったり、滅失・毀損により契約の目的を果たせなかったりする場合、買主は無条件で契約の解除が可能です。
稀なことではありますが、万が一の時のことを考えて危険負担についてしっかり確認しましょう。
契約不適合責任やその他の契約違反による解除
不動産売買契約書には、上記で解説した契約不適合責任について明記されているのが一般的です。
売主が契約不適合責任を負う範囲や期間などの特約はしっかり確認しておきましょう。
また、その他に契約違反による契約解除の旨も記載されています。
一般的に契約違反を理由に契約解除が行われる場合、違約金や解約金の支払いが生じる条件となっていることが多いです。
また、違約金の相場は売買代金の20%が相場なので、過度に高い金額になっていないか確認しましょう。
反社会的勢力の排除
不動産取引では、反社会的勢力排除のための条項の導入が推奨されています。
「売主・買主が反社会的勢力に属していないこと」「物件を反社会的勢力の活動拠点として提供しない」などの条項があることを確認してください。
この条項があれば、反社会的勢力のつながりがなく、安心して取引ができます。
万が一に条項に反した行為が行われていれば、契約解除を求めることが可能なので、しっかり確認しておきましょう。

INA&Associates Inc.は、不動産、IT、投資などにおける専門性と技術を活かし、高級賃貸・売買・事業用不動産仲介を中心とする総合不動産会社です。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫の賃貸管理、賃貸売買仲介、事業用不動産仲介・買取をメイン事業として展開しており、土地、マンションの有効活用の企画・提案、外資系法人の転勤者向けの社宅仲介も行っております。
不動産売買契約で手付金はいくら必要?

不動産売買契約の際、買主は売主に手付金を支払うことになります。
そもそも手付金とは何か、またどのくらいの相場なのかみていきましょう。
不動産売買契約で発生する手付金とは?
手付金は、売主に向けて契約の履行を保証する意味で支払うお金で、以下3つの種類に分けられます。
・証約手付:契約を締結した証に交付される手付
・解約手付(手付解除):解約の代償として支払う手付
・違約手付:売主か買主に債務不履行があった際に、違約金として相手方に没収される手付
基本的には契約を締結した証として買主が売主に支払うお金ですが、解約や契約違反があった際の保証にもなっています。
解約手付の場合、買主都合での解約なら手付金の返還を請求することはできません。
反対に売主都合で解約となった際は、倍額で買主に返還する必要があります。
ちなみに手付解除ができるのは、「相手が履行に着手するまで」とされているので、すでに契約書で定められた約束が実行されていると、解除できないので注意してください。
また、売主と買主のどちらかに契約違反が発覚した際、相手方に賠償請求ができますが、それとは別に罰則の意味合いで手付金が没収される、または倍額で支払うことになります。
相場は売買代金の5~20%
一般的には売買代金の5~20%が相場ですが、民法によれば、手付金の金額は当事者同士で自由に決めることが可能です。
金額が少なすぎれば解約されやすくなり、反対に金額が大きいと解約の難しさから契約が成立しない可能性があります。
そのため、相場の5~20%を目安に決めるのが妥当と言えます。
なお、売主が不動産会社となるケースでは、法律によって売買代金の20%以内と定められています。
契約書をチェックする際は、法律に触れる手付金額になっていないか確認しましょう。

Webサイトやオウンドメディアは、企業の想いや価値観を社会に伝える重要な手段です。
専門担当者の不足、ノウハウの不足、コストの不安などの理由で後回しになっていませんか?
私たちは、「人間的想像力 × テクノロジー」を最大限に活用し、企業が持つ本来の魅力を明確に可視化。社会から正当に評価される状態へと導きます。
不動産売買契約に必要な書類を準備しよう
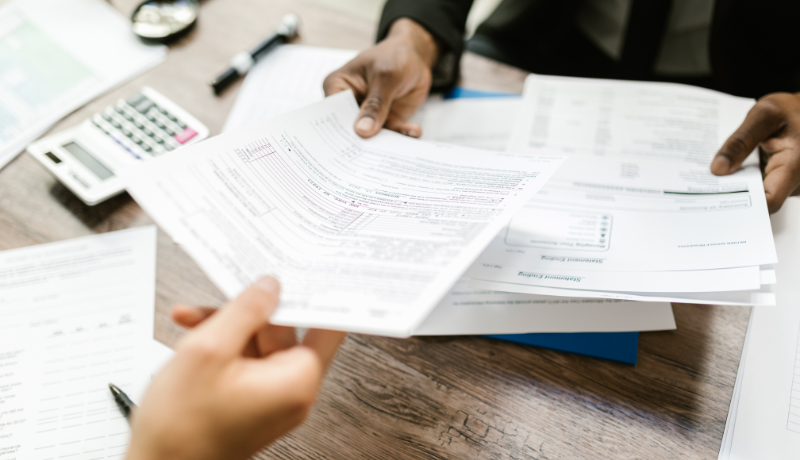
不動産売買契約を結ぶ場合、書類を準備しなければいけません。
続いては、売買契約を結ぶ時、決済をする時、引き渡しをする時に必要な書類について解説していきます。
売買契約を結ぶ際に必要な書類
売買契約を結ぶ際、売主と買主の両方が準備するのが身分証明書と印鑑です。
また、売買契約書に添付する収入印紙も必要になりますが、不動産会社が用意します。
そのため、売主と買主は印紙代を不動産会社に支払うだけで済みます。
売主はその他にも、以下のような書類を用意しなければいけません。
・住民票
・印鑑証明書
・銀行口座
・固定資産税納税通知書など
・建築確認済証、建築設計図書など
・マンションの管理規約、維持費等の書類など
・耐震診断報告書など
・設備表
・物件状況等報告書
決済時に必要な書類
決済時に売主と買主が準備する書類は以下のとおりです。
・身分証明書
・印鑑
・印鑑証明書
・住民票
また、売主は以下の書類も用意しておかなければいけません。
・登記識別情報または登記済権利証
・抵当権抹消書類
引き渡し時に必要な書類
引き渡し時に必要な書類には、以下のようなものが挙げられます。
・登記識別情報または登記済権利証
・印鑑証明書
・住民票
・固定資産評価証明書
・司法書士への委任状
・印鑑
・実測図、境界確認書
・残代金や清算金の領収書(口座振替に控えでも可)
・建築関係書類
引き渡し時に鍵も渡さなければいけないので忘れないようにしましょう。

INA&Associates Inc.は、不動産、IT、投資などにおける専門性と技術を活かし、高級賃貸・売買・事業用不動産仲介を中心とする総合不動産会社です。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫の賃貸管理、賃貸売買仲介、事業用不動産仲介・買取をメイン事業として展開しており、土地、マンションの有効活用の企画・提案、外資系法人の転勤者向けの社宅仲介も行っております。
不動産売買契約を締結する際の流れ

不動産売買契約を結ぶなら、どのような流れで行われるのか知っておく事も重要です。
そのため次は、不動産売買契約を締結する際の流れについて見ていきましょう。
媒介契約を結ぶ
媒介契約は、買主を見つけてもらうために不動産会社と結ぶものです。
売主が自力で買い手を見つけるのは難しいので、不動産を売りたいと考えた時は不動産会社と媒介契約を結ぶケースが多いです。
買い付けの申し込みをする
媒介契約を結ぶと、内覧などを行った後、購入を検討している人から不動産会社経由で買い付けの申し込みがあります。
買付の申し込みが入ったら、手付金を受領することになります。
売買契約書と重要事項説明書の打ち合わせを行う
次に、不動産会社と売買契約書と重要事項説明書の打ち合わせを行います。
内容に漏れや誤りがないかチェックするための必要なステップです。
この間に不動産会社から購入を検討している人に対し、住宅ローンを活用するなら事前審査を行ったり、契約に必要な書類の取得を依頼したりします。
重要事項説明を行う
重要事項説明書は、あらかじめ購入を検討している人に送付し、目を通してもらいます。
そして、重要事項説明を不動産会社にしてもらいましょう。
契約の当日に対面した上で行うのが一般的ですが、最近ではIT重説を取り入れるケースも増えています。
IT重説は、買主が遠方に住んでいたり、多忙だったりして、日程調整がうまくいかない場合に調整しやすくする役割を担っています。
従来は対面での説明が義務付けられていましたが、IT重説の導入によってテレビ会議システムなどを使ったオンラインでの説明が可能となったためです。
契約、決済、引き渡しを行う
重要事項説明を行ったら、売買契約の締結を行います。
契約時には、前述したような書類が必要となるので抜かりなく用意しておきましょう。
契約を締結したら、決済(自己資金もしくは住宅ローンの入金)を確認し、登記手続きを行います。
すべて完了したら、不動産の引き渡しを行うことになります。
また、契約当事者間で決めた期日までに明け渡しができない場合は契約不履行となってしまうので注意しなければいけません。

Webサイトやオウンドメディアは、企業の想いや価値観を社会に伝える重要な手段です。
専門担当者の不足、ノウハウの不足、コストの不安などの理由で後回しになっていませんか?
私たちは、「人間的想像力 × テクノロジー」を最大限に活用し、企業が持つ本来の魅力を明確に可視化。社会から正当に評価される状態へと導きます。
不動産売買契約で気を付けたいこととは?

不動産売買契約は、簡単に解除できないので注意点についても把握しておく必要があります。
ここでは、具体的にどのような点に気を付けるべきなのか、3つピックアップしてご紹介します。
契約は簡単に解除できない
不動産売買契約を結ぶと、簡単に解除することができません。
やむを得ない事情で解除を申し入れる時は、契約時に決めた「解除の条件」に基づいて違約金を支払わなければいけない場合もあります。
契約違反が原因で解除になってしまった時は、不動産売買代金の10~20%という重たい違約金が発生する点も念頭においておきましょう。
3,000万円の一戸建てであれば、違約金は300万~600万円が相場となります。
また、買主が住宅ローンの審査に落ちてしまった場合に備えて、契約を白紙に戻せる「ローン特約」も盛り込むようにしてください。
契約解除の種類に関しては、後ほど詳しく解説します。
契約不適合責任に要注意
契約不適合責任は、売買契約で契約内容を満たさない不都合が生じた時、売主が買主に対して負う責任を指します。
具体的には以下のような点が挙げられます。
・購入した物件が雨漏りしていたのに告げられていなかった
・水漏れがあるのに説明されなかった
・シロアリ被害について伝えられていなかった
このような事態があった場合は、買主は売主に補修を求められます。
売主が応じない時は、代金の減額や損害場仕様を請求される可能性があります。
ただし、契約不適合責任は買主との合意があれば売買契約書の特約で免責にできます。
免責にしてもトラブルが起こる可能性までゼロにできないので、懸念事項を1つずつピックアップし、どこまでが免責事項になるのか明確にしておかなければいけません。

INA&Associates Inc.は、不動産、IT、投資などにおける専門性と技術を活かし、高級賃貸・売買・事業用不動産仲介を中心とする総合不動産会社です。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫の賃貸管理、賃貸売買仲介、事業用不動産仲介・買取をメイン事業として展開しており、土地、マンションの有効活用の企画・提案、外資系法人の転勤者向けの社宅仲介も行っております。
不動産売買契約を解除することは可能?

不動産売買契約を解除することは、できる場合とできない場合があります。
前述したように契約の解除は簡単ではありません。
最後に、契約解除の種類や違約金を支払わずに解除できるケースについてご紹介します。
契約解除の種類
契約解除には以下のような種類があります。
・手付解除
相手方が契約の履行に着手する前に行えるのが手付解除です。
売主側が手付金の倍返しをしたり、買主側が放棄したりすることで契約を解除できる方法になります。
・危険負担による解除
台風や地震、洪水などの天災で取引予定の物件が毀損してしまい、修繕費用が多額になる場合、売主は無条件で契約の解除ができます。
このような場合、売主は買主に対し、手付金や売買代金の返還を行う特約を付けるのが一般的となっています。
・瑕疵担保責任に基づく解除
建物に重大な欠陥などの瑕疵があった場合は、その瑕疵で契約の目的を果たせない可能性が出てきます。
契約の内容に齟齬が生じるので、買主は無条件で契約を解除できるのです。
・契約違反による解除
売主または買主のいずれかが契約に違反したら、違約金などの支払いによって契約を解除できます。
例えば、相手が契約書どおりに進めなかった場合などが挙げられるでしょう。
期日を指定して催促したにもかかわらず、応じてもらえないケースもないとは言い切れません。
そのような場合、契約を解除し、違約金を請求できます。
・特約による解除
特約の内容によって、それが解除理由になる場合もあります。
例えば、買主が住宅ローンを受けられなかった時に無条件で契約解除できるローン特約などが該当します。
・クーリングオフによる解除
クーリングオフは、買主から一方的に契約できる制度ですが、以下の条件を満たす必要があります。
・売主が宅建業者、買主が宅建業者以外である場合
・ファミレスや喫茶店、案内所など公の場所で契約している
・期限は、不動産会社からクーリングオフ関する説明や書面を交付された日から8日間
これらの条件を満たしていれば、買主側からクーリングオフされる可能性があります。
・消費者契約法に基づく解除
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外であれば、消費者契約法に基づく解除ができる場合もあります。
消費者契約法は、消費者が誤認または困惑した場合、契約の申し込みや承諾の意思を取り消すことができると盛り込まれた法律です。
売主側が何としても売りたいと思って事実とは異なる内容を伝えたり、間違えた情報を伝えたりした場合、買主は契約を解除できることになります。
ただし、催告してから解除へと進むので、すぐに解除となるわけではありません。
・合意による解除
売主と買主が合意した条件で契約を解除することももちろん可能です。
違約金を支払わずに解除できるケース
契約を解除する際は、基本的に違約金が発生します。
しかし中には、違約金を支払わずに解除できるケースもあるのです。
どのようなケースで違約金の支払い義務が消失するのかチェックしておきましょう。
・相手が債務不履行の状況になったケース
債務不履行は、契約後にやらなければいけないことを完了させていないことを指します。
不動産売買では、期日までに物件の引き渡しを行わない、売買の代金を支払わない、といったものが挙げられるでしょう。
一定期間催告をしても行動してくれない場合に成立となります。
相手が取引に向けた行動をしてくれないのであれば、不動産会社に相談してみてください。
不動産会社はプロなので、状況に合わせて適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
・やむを得ない事情が生じたケース
物件が天災で減失してしまった、当事者が病気で働けなくなってしまった、当事者が死亡してしまった、といった場合、やむを得ない事情だと判断される可能性が高いです。
誰の責任でもありませんが、契約を履行できない状況です。
そのような場合は、違約金が発生しないケースが多く見られます。
しかし、絶対に違約金が発生しないとは言い切れないので、不動産会社に確認しておくと安心です。
もしこのような事態に陥ったら、焦らず不動産会社に相談してみてください。
不動産売買契約を解除する際の注意点
不動産売買契約を解除する時、いくつか把握しておきたい注意点もあります。
契約解除となる可能性をなくすことはできないので、解除時の注意点は把握しておきましょう。
・手付金の放棄による解除は相手が履行する前に行う
契約解除は、基本的に相手が履行する前に行います。
いずれかが代金の支払いや物件の引き渡しなどを行ってしまうと、解除ができなくなってしまうのです。
トラブルを回避するためにも、売買契約は慎重に進めるべきだと言えるでしょう。
・違約金を受け取ったら確定申告をしなければいけない
売主側でも買主側でも、相手からの申し出で契約を解除するとなった場合、手付金や違約金が発生します。
それらのお金は、課税対象であることを忘れてはいけません。
手付金や違約金は一時所得とみなされるので、所得税と住民税を支払う義務が発生するのです。
そのため、手付金や違約金を受け取ったら年の翌年には、確定申告を必ずしてください。
確定申告の期間は2月16日~3月15日です。
・買主の都合で解除する場合は不動産会社に違約金を支払う
不動産売買契約には法的な拘束力があります。
そのため、何らかの理由で契約解除となった場合、これまでにも説明したように基本的には違約金がかかります。
買主の都合で不動産売買契約が解除になると、仲介していた不動産会社は仲介手数料が入らなくなってしまうのです。
仲介手数料は成功報酬なので、契約が成立しなければ不要になるものだと考える人も少なくありません。
しかし、契約を1回交わしているので、不動産会社は報酬を請求する権利が認められています。
実際に請求されるかどうかは不動産会社によるのではっきりと言えませんが、仲介手数料と同じ金額を買主に対して不動産会社が請求する可能性は大いにあります。
買主側は解除してしまえば問題ないと思うかもしれませんが、そうではないことを念頭に置いておかなければいけません。
不動産売買契約は、正しい知識を身に付けた上で結ぶ必要があります。
契約解除や損害賠償請求にもつながる「契約不適合責任」や不動産売買契約書でチェックすべきポイントなどをしっかりと理解しておかないと、後々トラブルになってしまう可能性が高いです。
不動産売買契約に必要な書類や不動産売買契約を締結する際の流れ、注意点などの基本事項も把握しておけば、トラブルを未然に回避できるでしょう。
不動産売買契約を結ぶ時は、今回紹介したポイントを念頭に置いた上で進めるようにしてください。
また、契約解除についても把握していれば、万が一の時も安心です。
売主と買主の双方が納得できるような契約を結ぶためにも、不動産売買契約の基本を把握しておくことは重要だと言えるでしょう。
