近年、自然災害が各地で起こっています。
これにより、今まででは考えにくい災害が局地的に起こることが多く、普段の備えではどうにもできないこともあるでしょう。
そこで、災害後などに修理が生じた場合に税負担を軽減できる雑損控除について解説していきます。
雑損控除の計算方法、確定申告の際の方法、雑損控除と災害減免の違いについても説明していくので、この記事を参考にしてみてください。
Contents
雑損控除とは?
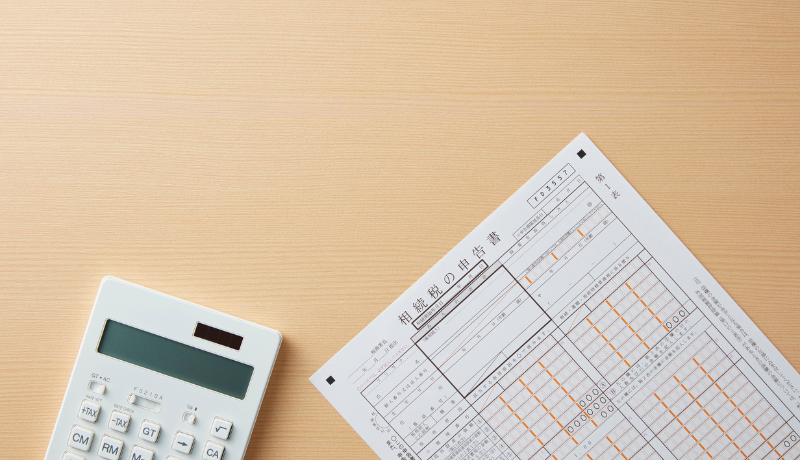
雑損控除とは、どのような控除なのでしょうか?
雑損控除は、所得控除のなかのひとつであり、所得税から差し引くことができます。
災害、盗難、横領などで資産が損害を受けた時、確定申告で一定の所得控除を受けられるものです。
損害額によって税金が安くなりますが、金額が大きい場合は翌年以降3年繰り越して控除が受けられます。
この控除を受ける場合は確定申告が必要です。
雑損控除対象の内容について
ここでは、雑損控除の対象となる内容をみていきましょう。
盗難
盗難でも、雑損控除対象となる内容は以下のとおりです。
・駐車場に停めていた車(自家用車)が盗まれた
・電車で置き引きに遭って財布を盗まれた
・預金通帳が盗まれて不正な払戻しで被害に遭った
同じ盗難であっても、タンス預金、無くなった時期のわからないものに関しては紛失になるので雑損控除対象外です。
横領
横領は、税務上横領となって刑法で罪になります。
これによって雑損控除適用となりますが、詐欺や恐喝では受けられないので注意してください。
火災、火薬などの爆発など人為で起こった異常な災害
火災、火薬などの爆発が人為で起こった場合、雑損控除対象となります。
工場の爆発、火災などの他に、分譲マンション構造計画書の偽装被害物件に住んでいる居住者の自主退去費用なども対象です。
ただし、アスベストなどの除去費用は該当しないので気をつけましょう。
害虫などの生物によって起こる異常な災害
害虫、害獣など生物によって起こる災害も雑損控除対象です。
例えばシロアリによる被害があり、駆除するための費用は対象になりますが、被害防止のための費用、駆除と同時に行う予防費用に関しては対象外となります。
震災、冷害、雪害、風水害、落雷など自然現象の異変で起こった災害
予期せぬ自然災害に見舞われた場合は、雑損控除の対象になります。
例えば、台風によって大雨となった後に浸水、洪水などが起こった時の修繕費、雨漏りが起こった際の修理費、大雪による雪下ろし費用などが対象です。
雪による倒壊防止に購入した除雪関連費用、雪下ろし用に購入したスコップ代金、雪下ろしを依頼した人へ支給した食事代なども含まれます。
自然現象による災害に関しては、備えの費用も含まれるものがあるので税務署に確認しておきましょう。
雑損控除の対象となる資産について
雑損控除の対象となる資産にも条件があります。
資産の所有者が納税者、もしくは納税者と生計を一緒にする配偶者、その他親族で、その年の総所得金額等が38万円以下であることが条件です。
趣味、娯楽、別荘、保養や鑑賞目的で持っている不動産、貴金属、骨董、書画などは、1個または1組が30万円以上の価額となるものなどは、通常の生活に必要のないものとなり、雑損控除の対象外となります。
あくまで、雑損控除の対象となるのは生活に必要な動産であり、家具、什器、衣服などに類する生活用動産、通常の社会生活を送るうえで必要な資産が対象です。
これらの対象を踏まえて、家庭にある生活に必要な資産を考えてみましょう。
自宅家屋はもちろん、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの家電、通勤・通学用の自転車などが対象です。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
雑損控除における2つの計算方法

雑損控除の対象が何か理解できたら、実際に雑損控除を計算してみましょう。
雑損控除額は、以下のうちどちらか多い方となります。
【雑損控除の計算方法】
①差引損失額-総所得金額等の10%
差引損失額とは、損害金額+災害等に関連した支出金額-保険金等から補填される金額となります。
損害金額は、損害を受けた時の時価で計算します。
平成26年分から損害を受けた資産が減価償却資産の場合は、その資産を取得した時の金額から減価償却費累積額相当額が控除された金額となります。
これを基にして損害金額を計算するものです。
災害等に関連した支出金額は、災害で被害を受けたのが住宅そのものであれば、修繕、撤去、取り壊しなどの金額です。
保険金等から補填される金額は、災害などに関連して受け取った保険金、損害賠償金などとなります。
②差引損失額から災害関連で支出した金額-5万円
災害関連で支出した金額は、災害などで失った住宅、家財、取り壊し、撤去などで支出した金額です。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
確定申告で雑損控除を申告しよう
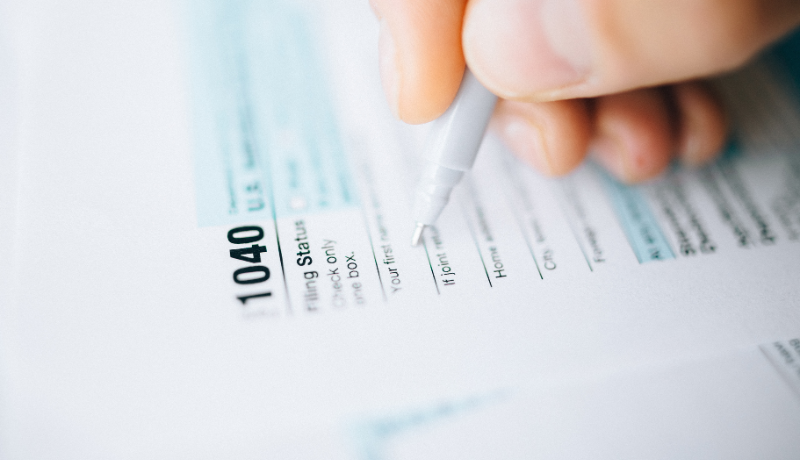
これらの内容を踏まえて、雑損控除を申告してみましょう。
雑損控除の申告方法は、確定申告書とe-Taxを使う場合があります。
ここでは、この2つの方法で申告手順をご紹介します。
領収書を用意しよう
雑損控除を受けるには、まず領収書を用意しなければなりません。
盗難の場合は被害届出用の証明書、火災が関係する場合は消防署、災害が関係する場合は支出金額がわかる領収書が必要です。
水害で多くのものが流されてしまい、証明書などが用意できない場合は、該当する資産を取得した際の価額、取得年月日のわかる書類など、損失額がどれくらいかを証明できる書類があれば申告できます。
これらを用意したうえで、確定申告を行いましょう。
確定申告ですが、申告内容が雑損控除のみ、または確定申告書提出義務のない方の場合、雑損控除と医療費控除など、所得税還付がある申告の場合は、受けられる年分の翌年から5年間いつでも確定申告できます。
被害を受けた直後に慌ただしさから申告できないという場合でも、証明書類を残しておくことで5年前まで戻って申告できるので安心です。
被災した場合は災害減免法の対象になる可能性もあり、これによって計算した結果額の所得税額から直接減税ができます。
所得合計額が1,000万円以下、損害額から保険金などの補填金額以外が住宅や家財の額の1/2以上なら対象なので、確認してみましょう。
書類による申告方法
書類提出で雑損控除をしていきましょう。
確定申告書類には、第一表と第二表があります。
第二表は、中央右側に「雑損控除に関する事項」という項目があり、雑損控除原因や損害金額などを記入します。
ここには、以下の内容を記載する必要があります。
【記載内容】
・損害の原因
・損害年月日
・損害を受けた資産の種類など
・損害金額
・保険金などで補填される金額
・差引損失額のうち災害関連支出の金額
損害の原因は、何が原因で損害を被ったのかを記載します。
火災、盗難、災害などについて書きます。
損害を受けた資産の種類などでは、住宅、家財などがあれば書きますが、2つ記入しても問題ありません。
損害金額は、損害を受けた合計額を記載し、その後保険金などで補填される金額を記載してください。
差引損失額のうち災害関連支出の金額については、家屋の撤去、取り壊し、修繕などにかかった金額を書きます。
これらが書き終わったら、第一表の方も記入していきましょう。
ここでは、第二表に記した数値から算出した雑損控除の金額を書きます。
「所得から差し引かれる金額」という項目内にある「雑損控除(26)」に記入します。
申告書の提出期限について
続いて、申告書の提出期限についてです。
確定申告書は、税務署の窓口に提出する、税務署に郵送する、e-Taxで提出する方法で行います。
提出期限は、2月16日~3月15日の1ヶ月間です。
書類は、自分の住所を基に管轄する税務署宛に提出します。
もし、直接税務署に持ち込む場合は開庁時間に注意してください。
初めて確定申告をする場合、雑損控除をする場合は、必要な書類を持っていくと教えてもらいながら記入できます。
時間はかかってしまいますが、確実にできるのでおすすめです。
過去に経験がある場合は、相談せずに申請書類を時間外収受箱に投函すれば問題ありません。
これらの方法以外では、e-Taxなら自宅から申告可能なので郵送や直接訪れることがないので便利です。
被災した場合は例外で申請できる
確定申告期間は、上記でも説明したように2月16日~3月15日の1ヶ月間です。
ただし、災害によって被災した場合は期限内に申告するのが困難なケースもあるでしょう。
日本では、被災した場合に限り、「地域限定による延長」「個別申請での延長」の措置を設けています。
「地域限定による延長」では、災害が起こった大きい地域一体で一斉に申告期限が延長されます。
東日本大震災では、大規模な災害によって岩手県、宮城県、福島県を中心に様々な特例措置が設けられました。
「個別申請での延長」は、災害によって申告、納付などの期限延長申請書を各自提出することで、災害から2ヶ月以内であれば申告や納付が可能というものです。
新型コロナウイルス流行期には、経理担当者不在によるものであったり、濃厚接触者になったりしたことで思うように申請できなかった人に対して利用されました。
e-Taxによる申告について
続いて、e-Taxによる申告についてご紹介します。
e-Taxは、国税電子申告・納税システムと呼ばれるもので、国税庁が管理しています。
税に関する申告、法定調書の提出などの各種手続きがインターネットでできるシステムです。
e-Taxを利用すれば、自宅や会社からでも申告や納税の手続きを済ませることができ、さらにe-Tax対応の会計ソフトを使用することで、会計処理などのデータ作成から提出まで済ませられるメリットがあります。
e-Tax対応の会計ソフトを使う場合の申請方法
続いて、e-Taxを使った申請方法についてご紹介していきます。
e-Taxを使って確定申告を行う場合、確定申告書作成、e-Taxでの申告から選択可能です。
個人事業主なら、青色申告決算書、収支内訳書も必要になるので用意しておきましょう。
e-Taxに対応している会計ソフトを使用している場合は、帳簿の作成、集計、確定申告書作成、送信までスムーズに行うことができます。
直接書く場合、どこに書いたらいいのか迷うこともありますが、自動仕訳やデータの取り込みによって作業短縮が可能です。
確定申告書作成も早くできるだけでなく、そのままe-Taxから送信できるのも大きなメリットでしょう。
ただし、これはe-Tax対応している会計ソフトでの方法になります。
対応していない会計ソフトの場合は、確定申告書作成と、e-Taxでの申告が別々の作業になることを忘れないようにしてください。
会計ソフトがあれば、雑損控除などを含めて作成することは簡単ですが、e-Tax利用時には別のソフトが必要です。
国税庁のサイトから作成する
会計ソフトがなく、e-Taxと連携できない場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなら会計ソフトなしでも確定申告書作成が可能です。
手書きなどで帳簿を付けている場合は、集計した数字をガイドに従って入力していくだけです。
作成ページからそのままe-Taxで電子申告する方法、プリントアウトして税務署の窓口に提出する方法もあります。
スマホから作成する
雑損控除を申請したい場合は、パソコンがなくてもスマホから行う方法もあります。
スマホから確定申告する場合も、パソコンと同じように確定申告書作成、e-Taxでの申告から選択可能です。
スマホからでも国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、簡単に確定申告書が作れます。
スマホの場合、雑損控除を含めた所得控除は全て対象となっていますが、税額控除やその他などはできないものもあります。
雑損控除の他の申告をしたい場合は、スマホからも申告できるものかどうかを確認してから行いましょう。
e-Taxソフト(SP版)から作成する
確定申告書は、e-Taxソフト(SP版)を使えば、より簡単に申請できます。
e-Taxソフト(SP版)で使用できる機能は以下のとおりです。
【e-Taxソフト(SP版)で利用できること】
・利用者登録・確認
・納税手続き
・変更申請
・送信確認
・お知らせなどの確認
これらの内容は、「国税庁のスマホとマイナンバーカードでe-Tax!」で詳しく記載されているので参考にしてみましょう。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-etax.htm
e-Taxで確定申告した場合のメリット
e-Taxで確定申告した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
【メリット】
・第三者作成書類の提出不要
e-Taxを使うと、決められた第三者作成書類の提出は不要です。
ただし、書類は必要なくても操作画面には数値の入力が必要なので、間違えないようにしましょう。
また、法定申請期間から5年間は保管しておかなければならないので注意してください。
・早く確定申告できる
確定申告受付期間は2月16日~3月15日ですが、e-Taxでは1月上旬からデータ送信ができます。
混みあう前に申告できるのもメリットでしょう。
【デメリット】
・環境を整える必要がある
e-Taxを使う場合、利用者の識別番号を取得する必要があります。
スマホの対応機種、ICカードリーダーなどが必要になってくるため、環境を整える手間がかかるでしょう。
・初めてだと難しい場合がある
パソコンやスマホでの操作がメインなので、初めての場合はどこに何を記入したらいいのかわからないことも多いでしょう。
機械の捜査が苦手な方には、利便性よりも難しさがデメリットになる可能性があります。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
雑損控除を受けるために必要な書類
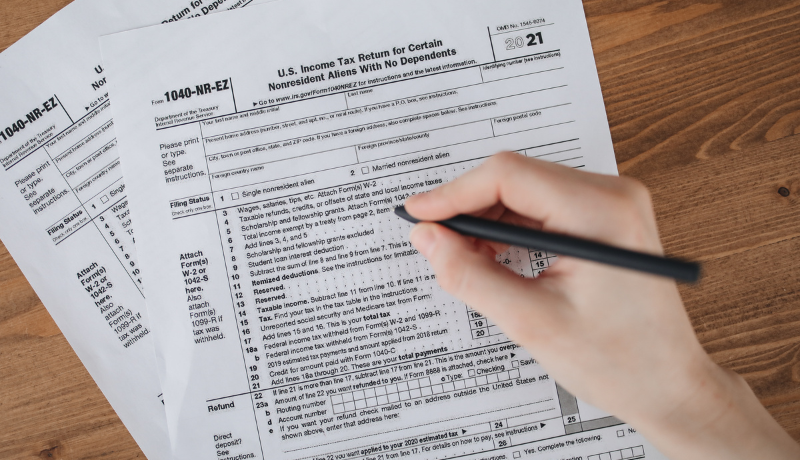
雑損控除は上でも紹介した計算式で出した金額の根拠を示すために、書類を提出しなくてはいけません。
ここでは、雑損控除を受けるために必要な書類について、詳しく解説します。
被害を受けた資産の取得時期や取得価格がわかるもの
雑損控除を受けるには、被害を受けた資産の取得時期や取得価格のわかる書類が必要です。
建物の請負契約書など、購入時期や購入価格のわかる書類を準備しておきましょう。
やむを得ない支出を証明する書類
雑損控除では、災害によって被害を受けた資産を取り壊したり、修繕したりと関連したやむを得ない支出をした金額がわかる書類が必要です。
見積もり書や領収書などが取り壊し費用や修繕費がわかる書類として認められているため、やむを得ない支出があった場合は、これらの書類も用意しておきましょう。
保険金に関する書類
保険金を受け取った場合、保険金の支払い証明書が必要です。
保険会社から発行されるので、保険金等を受け取った場合は書類を用意しておきましょう。
なお、義援金や弔慰金、支援などは、原則差し引く必要はありません。
したがって、申請時には明細も不要です。
所得金額に関する書類
雑損控除を受けるには、1年間の所得金額を証明する必要があります。
賃貸経営のためにしている決算書などで構わないので、年間の所得金額を証明する書類を用意しましょう。
罹災証明書(写し可)
罹災証明書とは、自身や台風などの自然災害によってどの程度の損害を受けたかを証明する書類です。
被災者からの申請に基づき、各自治体が被害の程度を判定します。
自分から申請しないと調査してもらえないため、注意が必要です。
忘れずに調査申請を出すようにしましょう。
被害額届出用の証明書
火災によって被害を受けた場合は消防署、盗難によって被害を受けた場合は警察が発行する被害額届出用の証明書が必要です。
もしも、どちらかに該当する場合は、警察署もしくは消防署に被害額届出用の証明書を発行してもらいましょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
雑損控除でどれくらい負担が軽減されるのか?

雑損控除を受けると、税金の負担額にどのくらいの変化があるのか、詳しく見ていきましょう。
なお、雑損控除では以下の式のうち、控除される金額が高い方が適用されます。
①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
ケース1
年間所得金額は500万円です。
災害により4,000万円の損害を受け、さらに関連した支出が1,000万円です。
保険金として3,000万円を受け取っています。
この場合、損害額は、4,000万円+1,000万円から保険金3,000万円を引いた2,000万円になります。
①の計算式の場合
2,000万円-500万円×10%=1,950万円
②の計算式の場合
1,000万円-5万円=995万円
②よりも①の方が高いため、適用されるのは①の計算式となり、1,950万円が雑損控除の金額となります。
ケース2
年間所得金額は400万円です。
災害により、1,000万円の損害を受け、関連した支出の金額も1,000万円です。
保険金は1,000万円受け取っています。
このケースの場合、損害額は1,000万円+1,000万円から保険金1,000万円を差し引いた残り1,000万円となります。
①の計算式の場合
1,000万円-500万円×10%=950万円
②の計算式の場合
1,000万円-5万円=995万円
よって、適用されるのは②の計算式であり、995万円になります。
ケース3
年間所得金額は500万円です。
災害によって受けた損害額は500万円、関連したやむを得ない支出はありません。
保険金は500万円受け取っています。
この場合、損失額500万円から保険金500万円を差し引くため0円となります。
①の計算式の場合
0円-500万円×10%=-50万円
②の計算式の場合
0円-5万円=-5万円
どちらも損害額がマイナスとなり、0以下のため、雑損控除の適用はありません。
雑損控除が適用されると所得税と住民税の税負担が軽減される
通常、所得税や住民税は年間所得から給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などが差し引かれた課税所得にかけられます。
年収が500万円、給与所得控除が144万円、基礎控除が48万円、社会保険料控除が72万円の場合、
500万円-144万円-48万円-72万円=236万円
つまり、課税所得236万円に所得税や住民税がかけられることになります。
しかし、雑損控除を受けた場合、ここからさらに計算式で出た金額が適用され、課税所得が少なくなります。
課税所得が少なくなれば、その分所得税や住民税も少なくなるため、結果的に税負担が軽減されることになります。
なお、社会保険料控除や住民税控除の金額は、自治体によって異なります。
上記の数字はあくまでも一例です。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
雑損控除と災害減免は何が違う?

雑損控除と災害減免法は、どちらも地震や台風などの災害によって損害が生じた際に、税金が軽減される制度です。
似ているように見えますが、雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除と控除の方法が異なります。
以下では、それぞれの制度について、詳しく解説していきます。
雑損控除と災害減免法の違い
まず雑損控除と災害減免法では損失の対象が異なります。
災害減免法は、災害による損失が対象ですが、雑損控除では、盗難や横領による損失も対象となります。
また、対象となる資産についても、災害減免法は住宅及び家財が対象であり、損害金額は住宅あるいは家財の被害額が時価の1/2以上、年間所得が1,000万円以下である必要があります。
一方、雑損控除は、住宅や家財を含む、生活に必要な資産も対象で、主な適用条件はありません。
ただし、対象はあくまでも生活に必要な住宅や家財のため、別荘や賃貸用マンションのほか、30万円を超える貴金属や骨董品などの資産は除きます。
雑損候補と災害減免法を選ぶ基準とは?
雑損控除と災害減免法のどちらが良いかは、個々の条件によって異なります。
災害減免法には、所得金額が1,000万円以下、被害額が時価の1/2以上、盗難や横領などは対象外といった適用条件があるため、照らし合わせてみた結果、用件を満たしていないのであれば、雑損控除を選ぶことになるでしょう。
どちらの適用条件も満たしているのであれば、どちらの制度が有利なのか、試算して判断する必要があります。
雑損控除と災害減免法の注意点
雑損控除と災害減免法はどちらか一方しか適用することはできません。
重複して申請はできないため、どちらが自分にとって有利なのか、計算した上で判断しましょう。
また、雑損控除と災害減免法はどちらを受けるにしても確定申告が必要になります。
確定申告の期間は原則2/16~3/15のため、災害に遭った時期によっては手続きまで1年近くかかることがあります。
手続きのし忘れがないように注意しましょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
雑損控除に関するQ&Aまとめ
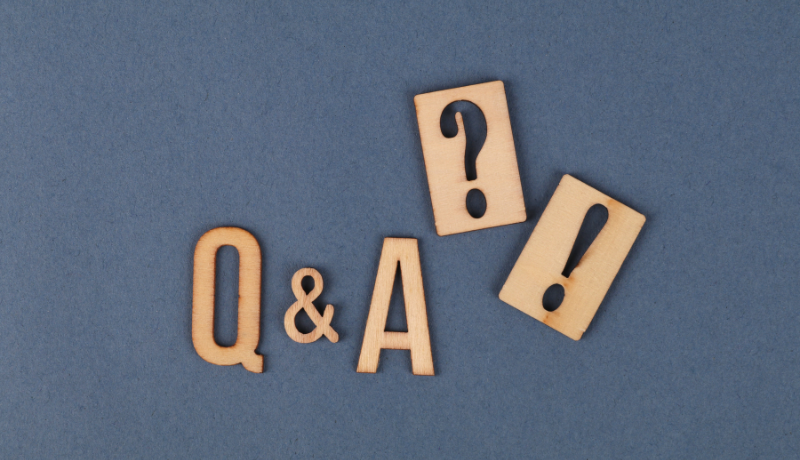
雑損控除に関してよくある質問とその回答をまとめました。
雑損控除に関連することで気になる点はないか、ぜひ確認してみてください。
雑損控除を年末調整で適用することは可能?
年末調整とは、所得税の過不足をなくすための手続きを指します。
会社では従業員一人ひとりの所得税を代わりに納めており、社会保険料・住民税などと一緒に給与・賞与から天引きしています。
ただし、天引きしている所得税はあくまで概算によって算出されたもので、実際の税額とは異なる場合もあります。
1年間の所得額が確定した段階で改めて計算をし直すことで、正しい所得税額を納められるようになるのです。
この時、概算で徴収していた所得税と実際に納める税額が異なっていた場合、その過不足分を従業員に還付または追加徴収することになります。
年末調整はあくまで所得税の過不足をなくすための手続きになるため、雑損控除には対応していません。
給与所得者で雑損控除を受けたい場合は、別途確定申告を作成し、提出する必要があります。
過去の雑損控除は申請できる?
確定申告の期限が過ぎてしまうと雑損控除が受けられないのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、還付申告は5年前の確定申告分までさかのぼることが可能です。
例えば2023年3月に自然災害が発生して被害を被った場合、2024年1月~3月の間に確定申告をすれば雑損控除が適用されますが、時間が経っていたため申告を忘れてしまっていたとします。
それでも2029年1月~3月までに確定申告で手続きを行えば、雑損控除の適用は受けられるのです。
もし現時点で過去5年以内に被害に遭い、雑損控除の対象に含まれている場合は確定申告を行って控除の適用を受けましょう。
生活費を同じ口座・財布から出していれば住所が別でも適用される?
雑損控除の対象となる資産は、資産の所有者が納税者または生計を共にする配偶者、その他親族であり、その年の総所得金額等が38万円以下であることが条件とご紹介しました。
この「生計を共にする」とは「同居する」と異なり、同居をしていなくても問題ありません。
例えば配偶者が単身赴任で遠方にいる場合や、学校の寮で生活している子どもに生活費を送金している場合、病気・ケガの影響でしばらく入院生活を送っている場合などは、生計を共にしていると判断できます。
害獣・害虫被害による費用は雑損控除の対象になる?
害獣・害虫による被害が発生した場合、所得税法施行令に伴い雑損控除の対象になります。
例えばシロアリが発生し、家の基礎部分に被害をもたらしている場合、シロアリを駆除するための費用や基礎部分の修繕費用はすべて雑損控除の対象内です。
ただし、雑損控除の対象となるのはあくまでも「被害に遭った箇所」であり、被害の拡大や発生を防ぐための支出は雑損控除の対象に含まれません。
緊急で必要な措置のための支出に対する控除となるため、予防するための支出は対象にならないことを覚えておきましょう。
不正送金による損害は雑損控除の対象になる?
上記でも簡単にご紹介しましたが、詐欺による被害は雑損控除の対象にはなりません。
しかし、仮想通貨などの不正送金による被害は雑損控除の対象となる可能性が高いです。
なぜ詐欺被害は対象外なのに、不正送金による被害は対象になる可能性が高いのでしょうか?
そもそも雑損控除は災害や盗難、横領によって資産に損害が発生した際に受けられる所得控除です。
災害・盗難・横領というのは、本人の意思とは結び付かない事由から損失が発生した場合を指します。
例えば振り込み詐欺などは確かに騙されてしまい、資産に損失が発生しているものの、最終的に振り込むことを決めたのは本人の意思です。
そのため、雑損控除の対象には含まれないと判断されてしまいます。
一方、不正送金に関しては他者が不正アクセスによってID・パスワードを盗み出し、資産を自身の口座に送金させることを指します。
つまり、不正送金は本人の意思とは関係なく、資産に損失が発生しているため雑損控除の対象になり得るのです。
また、雑損控除が適用される条件として、損失した資産は生活に必要な資産だったかも重要なポイントとなります。
不正送金の場合は暗号資産取引所に預け入れていることから、生活に必要な資産ではないと考えるかもしれません。
しかし、暗号資産は法定通貨ではなくても代金の支払い手段として用いられたり、法定通貨と相互交換できたりすることから、生活に必要な試算ではないと判断できないのです。
こうした理由から、不正送金による損害は雑損控除の対象になる可能性が高いと言えます。
自然災害による墓地・墓石への損害は雑損控除の対象になる?
自然災害などの影響で墓地や墓石、仏壇などに損害が発生した場合も、雑損控除の対象になります。
これは墓地や墓石、仏壇が生活に必要な資産に分類されるためです。
墓石や仏壇の修理費や新品を購入するのにも数万~100万円以上する場合もあるため、少しでもコストを抑えるためにも雑損控除の適用を受けましょう。
事業用資産に損害が発生した場合は雑損控除の対象になる?
災害などの影響から事業用資産に損害が発生した場合、雑損控除の適用は受けられません。
ただし、「経費」や「純損失」などの項目で計上することは可能です。
例えば損害を受けてしまった事業用資産を修繕するためにかかった費用は、修繕費として計上できます。
場合によっては特別損失として取り扱うことも可能です。
特別損失として計上できると損益計算書では経常利益の金額が増加し、さらに固定資産の除去処理を行うことで節税につながる場合もあります。
まとめ
今回は雑損控除について詳しく解説してきました。
雑損控除は資産が損害を受けた場合に適用できる所得控除で、税金の一部を還付してもらえます。
ただし、対象となる範囲は細かく決められており、場合によっては対象外となるものもあるので注意が必要です。
5年間はさかのぼって雑損控除の適用を受けられるため、資産の損害を受けている方はぜひ雑損控除を適用するために確定申告を行いましょう。
