建ぺい率や容積率と聞くと、難しそうな印象を持つ方も多いでしょう。
確かに普段の生活では使うことがない言葉なので、そのようなイメージを持つのも仕方ありません。
しかし、賃貸物件の大家さんなら建ぺい率や容積率について把握しておいた方が良いと言えます。
そのため今回の記事では、建ぺい率・容積率の計算方法や建ぺい率・容積率ごとの建築できる建物、用途地域との関係性、緩和される条件などについて解説していきます。
Contents
建ぺい率・容積率とは?計算方法も解説!

理解を深めるためには、基本的な部分から知ることが重要になります。
そこでまずは、建ぺい率や容積がどのようなものか、どのような計算方法で算出されるのか、という疑問に答えていきます。
建ぺい率とは
建ぺい率は、敷地の面積とそこにある建物の面積の割合を指します。
建ぺい率が注目されるのは、行政によって上限が定められているからです。
住宅を建てる場合、100㎡の土地で建ぺい率が60%だと、建築面積は60㎡以内に収まるようにしなければいけません。
不動産会社がインターネットやチラシで公開・記載していることも多いですが、自分で調べることもできます。
自分で調べる時は、市区町村役場の都市計画課などに電話で問い合わせてみてください。
建ぺい率などの情報が書かれている「都市計画図」は、インターネット上に公開されている場合もあります。
そのため、ネットで検索してみるのも良いでしょう。
建ぺい率は地域ごとに定められているものです。
したがって、建ぺい率の上限が異なる地域にまたがっているケースもないとは言い切れません。
そのような場合は、面積の割合で建ぺい率が決まるので注意が必要です。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率の計算方法は、とてもシンプルです。
「建築面積÷敷地面積×100」という計算式で算出できます。
ただし、建築面積の考え方には注意が必要です。
ここで言う建築面積は、真上から建物を見下ろした時の広さ(水平投影面積)となっている点です。
つまり、1階と2階で建築面積が違う物件の場合は、広い方の面積を採用して建ぺい率を計算します。
容積率とは
容積率は、敷地面積と建物の延べ床面積の割合を指します。
延べ床面積は、すべてのフロアの面を合計したものです。
建ぺい率と同じように、容積率も行政による制限があります。
そのため、建物の面積を狭くして階数を多くすれば問題ないという考え方は通用しません。
容積率が制限されているのは、道路などの公共施設とのバランスをとったり、居住空間を確保したりするためです。
同じくらいの広さの土地がある分譲地を例に挙げて考えるとわかりやすいです。
2階建ての住宅ばかり建っている中に、5階以上のアパ-トやマンションが突然建設された場合、日当たりや風通しが悪くなってしまいます。
近隣住民の生活環境が害されることになるでしょう。
そのような事態を防ぐためにも、容積率は都市計画で定められているのです。
住宅などを建てる際は、容積率の制限も守らなければいけません。
容積率の計算方法
容積率は、「延べ床面積÷敷地面積×100」という計算式で算出できます。
計算方法は簡単ですが、前面道路規制というルールがあるので注意しなければいけません。
前面道路規制は、敷地に面している道路の幅員が12m未満の場合、その幅員に定数(地域によって異なる)をかけた数字の方が小さいとその数字が容積率の上限になるというものです。
例えば、容積率の上限が200%、4mの道路の面していて、定数が0.4だと考えて容積率を算出してみます。
この場合、4m×0.4×100=160%となります。
本来なら容積率200%までの建物を建てられますが、前面道路規制によって160%までに抑えなければいけません。
建ぺい率と容積率が定められている理由
建ぺい率と容積率は、どちらか片方だけ使われることはありません。
この2つの数字があって初めて、どのような建造物を建てられるのかが決まるのです。
同じ敷地でも、建ぺい率と容積率によって建築可能な建物は大きく変わります。
そのため、セットで使うことが重要になります。
また、住みやすさを維持するためにも、重要な役割を担っているのです。
建ぺい率は、建物の平面的な広さを制限するもので、防災や風通しの維持が目的となっています。
すべての土地が建物で埋め尽くされてしまうと、火災などが起こった時の被害も大きくなってしまいます。
そのような事態を避けるためにも、土地に対してゆとりのある建物を建てるように誘導していると言えるでしょう。
容積率は、人口を抑えることが目的です。
建物の大きさを制限することによって、その地域に住む人口が増えすぎないようにコントロールしています。
容積率が定められていれば、道路や下水道などのインフラのキャパシティを超えるほどの人口にならずに済みます。
このことから、建ぺい率や容積率が定められていることで、生活のしやすさが保たれていると言えるでしょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
建ぺい率・容積率ごとに建築可能な建物をチェック

建ぺい率・容積率ごとに建築可能な建物が異なります。
続いては、具体的な数字を用いて、どのような建物を建築できるのか見ていきましょう。
ここでは、敷地面積が100㎡だと仮定して考えていきます。
建ぺい率50%・容積率100%
建ぺい率が50%で容積率が100%の場合、建築面積と延べ床面積は以下のようになります。
・建築面積の上限:100㎡×50%=50㎡
・延べ床面積の上限:100㎡×100%=100㎡
2階建ての住宅であれば、1階と2階の面積をそれぞれ50㎡にできます。
3階建てだと、1階が40㎡、2階と3階がそれぞれ30㎡といった広さの建物を建てられるのです。
アパ-トやマンションなどは、国土交通省によって居住面積の指針が定められています。
3人暮らしの最低居住面積水準は40㎡となっているので、1室あたり40㎡必要だと仮定して考えてみましょう。
そうすると、建ぺい率が50%で容積率が100%の場合は、1階と2階に40㎡の居室が1つずつ設置可能となります。
複数の居室を構えることは難しいので、一戸建ての賃貸が適した土地だと言えます。
また、単身向けとして20㎡の居室にすれば4室確保できるので、大学などが近くにある場合は視野に入るでしょう。
建ぺい率60%・容積率200%
建ぺい率が60%で容積率が100%の場合、建築面積と延べ床面積は以下のようになります。
・建築面積の上限:100㎡×60%=60㎡
・延べ床面積の上限:100㎡×200%=200㎡
住宅を建てる場合は、3階建てまでならそれぞれの階の広さが約60㎡にできます。
平屋だと延床面積は85㎡ほどになるので、少し狭く感じる可能性が高いです。
アパ-トやマンションを建てる場合だと、以下のようなパターンが考えられます。
・各階30㎡×2室×3階建て:6室
・各階20㎡×3室×3階建て:9室
夫婦世帯や単身向けの居室なら、複数構えられるでしょう。
ただし、ファミリー向けで広めにしたい時は各階に1室ずつといった形になってしまいます。
建ぺい率80%、容積率400%
建ぺい率が80%で容積率が400%の場合、建築面積と延べ床面積は以下のようになります。
・建築面積の上限:100㎡×80%=80㎡
・延べ床面積の上限:100㎡×400%=400㎡
住宅を建てる場合は、3階建てまでならそれぞれの階の広さが約80㎡にできます。
アパ-トやマンションを建てる場合だと、以下のようなパターンが考えられます。
・各階40㎡×2室×5階建て:10室
・各階20㎡×4室×5階建て:20室
夫婦世帯や単身向けの居室なら、複数構えることができる建ぺい率と容積率です。
ファミリー向けであっても、10室ほど確保できるでしょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
用途地域と建ぺい率・容積率の関係性

建ぺい率と容積率は、用途地域とも密接な関係があります。
続いては、用途地域とは何か、どのような種類があるのか解説していきます。
用途地域とは
用途地域は、計画的な市街地を形成するため、用途に応じて13の地域に分けられたエリアのことです。
エリアごとに建物の大きさや種類などが制限されているので、地域によって住み心地や生活スタイルが変わります。
エリアが分けられているのは、住宅の隣に大規模な商業施設や工場などがあると日当たりが悪くなったり、騒音・郊外などの影響で住みにくい環境になったりするためです。
工場側も、大型トラックが通りにくい場所などに立地すると交通渋滞が発生しやすくなるなどのデメリットを感じかねません。
そうなってしまうと、その土地を購入したいと思えなくなってしまいます。
そこで国は都市計画法を定め、各自治体はその法律に基づいた都市計画を立てているのです。
都市計画では、以下のようなエリア分けがされています。
・都市計画区域:計画的に街づくりを進めるエリア
・都市計画区域外:人があまりいない地域で、とりあえず市街地化計画を行わないエリア
・準都市計画区域:人があまりいないが重要エリアとして、制限が設けられるエリア
都市計画区域に分けられたエリアは、さらに細分化されます。
・市街化区域:既に市街地を形成している区域または今後優先して計画的に市街地化を図るエリア
・市街化調整区域:農地や森林などを守るべきエリア
・非線引区域:計画的に街づくりをする予定はあるが、現状のままにしておくエリア
市街化区域は、21の地域特区に分かれていて、用途地域もその中に含まれているのです。
用途地域によって何が変わる?
用途地域によって、アパートの高さや建ぺい率・容積率の制限、斜線制限などが異なります。
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の場合だと、高さ制限があるので3階建て程度の低層アパートしか建設できません。
それ以外の地域では、特に高さ制限がないので気にする必要はないでしょう。
しかし、斜線制限は用途地域によって異なるため、適用される基準を確認しておかなければいけません。
13種類の用途地域を徹底解説
用途地域は13種類に分けられています。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 用途地域 | 特徴 |
| 第一種低層住居専用地域 | ・建物の高さが10mや20mに制限されている低層住宅のためのエリア。 ・低層のマンションや延べ床面積が50㎡以下の店舗の建築も可能だが、コンビニは不可。 ・一戸建て住宅や賃貸住宅やマンション、小中学校を建てられる。 |
| 第二種低層住居専用地域 | ・建物の高さが10mや20mに制限されている低層住宅のためのエリア。 ・延べ床面積は150㎡までの店舗が可能となるので、コンビニや飲食店も建てられる。 ・コンビニなどがあるので利便性の高さと閑静な住宅地のバランスを求めている場合に適している。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | ・中高層住宅向けのエリアで、建物の高さ制限はない。 ・2階建て以内で延べ床面積が500㎡以下の店舗を建てられる。 ・幼稚園~大学などの教育施設や病院、寺院、図書館なども建設可能となるので、利便性が高い。 ・3階以上の建物も建てられるので、戸数の多い分譲マンションも多くなる。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | ・建物の種類は、第一種中高層住居専用地域と同様。 ・2階建て以内で延べ床面積が1,500㎡以下の店舗や事務所などを建てられる。 ・商業施設が多くなるエリア。 ・閑静さよりも生活の利便性を求める場合に適している。 |
| 第一種住居地域 | ・住環境を守るための地域。 ・住宅以外の条件は、第一種・第二種中高層住居専用地域と同様。 ・3,000㎡までの店舗や事務所、ホテルの建設も可能。 ・駅からも近いので利便性も高い。 |
| 第二種住居地域 | ・住環境を守るための地域。 ・ボーリング場やカラオケボックスなども建てられるため、遊べる場所が格段に多くなる。 |
| 準住居地域 | ・道路の沿道で自動車関連施設などと立地し、それらと調和した住環境を保護するための地域。 ・国道や幹線道路沿いが指定されるケースが多い。 ・第二種住居地域で可能な建物のほか、車庫・倉庫・作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場・客席部分200㎡未満の劇場や映画館の建設も可能。 |
| 田園住居地域 | ・農業と調和した低層住宅の環境を守る地域。 ・幅広い建造物を建てることができ、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランも建設可能。 |
| 近隣商業地域 | ・日用品などの買い物ができる地域。 ・延べ床面積の規制がない。 |
| 商業地域 | ・銀行や映画館などが集まることを目的とした地域。 ・ターミナル駅の周辺などが指定されるケースが多い。 |
| 準工業地域 | ・軽工業の工場やサービス施設などが建つ地域。 ・住宅やホテルなどの建設も可能。 |
| 工業地域 | ・どのような工場でも建てられる地域。 ・ホテルや映画館、病院、保育施設などは建てられない。 |
| 工業専用地域 | ・工場専用の地域。 ・住宅を建てることはできない。 |

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
建ぺい率が緩和される条件とは

建ぺい率は、ある特定の条件をクリアすると緩和される可能性があります。
建ぺい率緩和によって、今までよりも広い建物が建築できるため、メリットと感じる場合もあるでしょう。
ここでは、建ぺい率緩和の条件についてご紹介します。
防火地域・準防火地域に建設する
これまで建築基準法第53条第3項で防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率10%緩和という条件がありました。
その後、改正法によって現行に加えて防火地域・準防火地域にある耐火建築物や準耐火建築物に関して建ぺい率10%緩和に変更となったのです。
耐火建築物は、主要構造部が耐火構造であることが建築基準法で定められていて、火災によって倒壊、延焼が起こりにくい構造の建物となるようにしなければなりません。
防火地域は、都市計画法第9条21項で住宅が密集した市街地での火災の危険性を防ぎ、もし火災が起こった場合でも被害を最小限にするために建材や建築方法などが制限されてある所となります。
準防火地域は、防火地域の外側に広範囲で指定されているもので、防火地域同様に火災を防いで被害を最小限にすることが目的です。
耐火建築物以外に準耐火建築物として認められていますが、防火地域に比べて緩やかな基準となっています。
このように、都市部や中心部では建物同士の密着度が高く、幹線道路沿いなど火災が起こっても被害を最小限にする必要性の高い地域が、防災地域に指定されているのです。
もし防災地域に建物を建てる際には、小規模でない以上耐火建築をしていない場合は建てることができません。
耐火建築物を防火地域・準防火地域に建設した場合、元々の建ぺい率に10%を加えて設計可能なので、上限が70%なら最大80%の建物が建築できます。
2面が道路に接する角地に建設する
建築基準法第53条第3項の規定では、2面が道路に接する角地の建設でも建ぺい率が10%緩和されます。
ただし、角地緩和が該当する条件に関しては、自治体によって規定が設けられていますが、多いのが広場や公園、川、水面などの表現です。
しかし、同じ「広場」という表現であっても、具体的な扱いに関しては全国で統一されていないため、「広場」でも北海道の各自治体と東京の各自治体では認識が異なる可能性があります。
詳しい内容に関しては、各自治体のホームページで確認すると良いでしょう。
ここでは、東京都と各自治体による違いをご紹介します。
東京都(特別区)
東京都の特別区に分類されている千代田区を例にご紹介します。
千代田区では、「建ぺい率の緩和」として、法第53条第3項第2号の規定を基に区長が指定する敷地は周辺の1/3以上が道路もしくは公園、広場、川などに類するものに接していて、かつ以下の敷地のいずれかに該当するものとしています。
二つの道路が隅角120度未満で交わる角敷地、幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地、道路境界線相互間隔が35m以上にならないもの、公園などに接する敷地またはその前面道路の反対側に公園などがある敷地で全2号に掲げている敷地に準ずるものとしています。
北海道(札幌市)
続いて、札幌市を見ていきましょう。
札幌市では、「街区の角にある敷地等の指定」として法第53条第3項第2号の規定として、指定する街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地を以下のようにしています。
各々の幅員は6m以上、和が18m以上、内角が135度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地周辺の1/3以上がそれらの道路に接するもの、各々の幅員は6m以上、和が18m以上の2つの道路に挟まれた敷地で、その敷地周辺1/3以上が道路に接し、かつ1/8以上が各々の道路に接するもの、幅員が6m以上の道路と広場、公園、河川などと接し、前各号に準ずるものとしています。
この内容からもわかるように、地域によって細かな基準に差があることがわかります。
また、同じ県内であっても異なる場合があるので、必ず確認してからにしましょう。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
建ぺい率や容積率以外の建築制限をチェック!
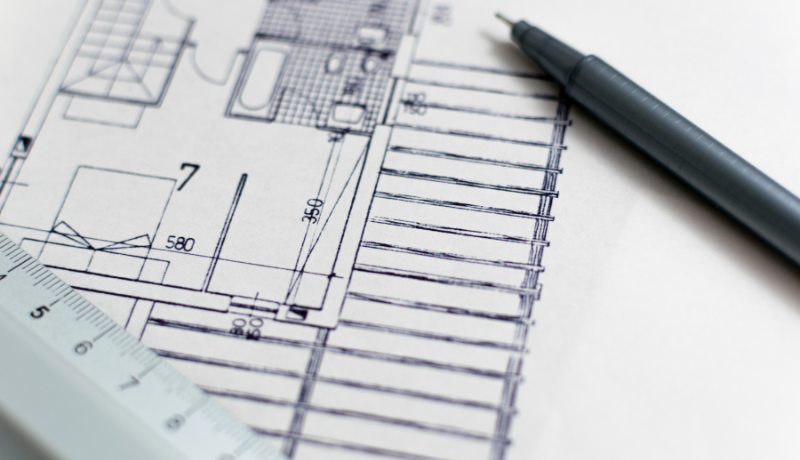
建物を建てる際に必要な建ぺい率ですが、気にしなければならないのは容積率だけではありません。
ここでは、建築制限がかかってしまう可能性がある制限についてご紹介します。
斜線制限
斜線制限とは、建物の高さを制限するものです。
これはどこの地域でも同じ高さではなく、環境によって差が生じます。
制限を設ける理由は、建物の高さを制限することで周辺の採光や風通しを妨げないようにするためです。
ここでは、3つの制限についてご紹介します。
隣地斜線制限
隣地斜線制限は、隣の土地に面している建物の高さを制限するものです。
道路以外の隣地との境界線によって決まりますが、一般的な戸建ての場合、隣地斜線制限対象外となりやすいです。
住居系地域では20m以上(6~7階建てマンションの高さ)の建物に対して制限が設けられています。
商業系地域、工業系地域では31m以上の建物に対しての高さ制限があります。
道路斜線制限
道路斜線制限は、建築する敷地に接している道路の反対側の境界線から敷地の方に向かって一定の距離以内の勾配に建物を収めなければならない制限です。
住宅系地域では道路の水平距離×1.25倍、商業系地域、工業系地域などその他の地域に関しては、道路の水平距離×1.5倍です。
北側斜線制限
北側斜線制限は、建物の北側に面している隣の土地の採光を損なわないためのものです。
北側にある敷地の境界線を基準にして、垂直に5mまたは10m上がった先の高さに規定の勾配線を引き、そこから直角三角形の作る角度となる1.25:1で設定し、その中に建物を収めなければなりません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域には絶対高さ制限があります。
このような制限に引っかからないように、北側に建物、南側に庭を作るケースがよくあります。
日陰制限
日陰制限は、太陽の当たり方によってできてしまう日陰が周囲の土地に一定時間以上かからないように制限するものです。
日陰の基準は各自治体の条例を基準に決められているため、必ず確認しておきましょう。
そのため、建物を建てる際にはそれぞれの環境で条件が変わることを覚えておくと安心です。
基本的には、一般的な2階建て程度の建物であれば制限内に収まることがほとんどです。
3階以上の場合は、制限を受けてしまう可能性があります。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住宅地域では軒の建物の高さ7m以上、もしくは3階以上の建物が規制の対象です。
その他は、高さ10m以上の建物もしくは制限なしとなります。
また、例外で日陰制限緩和が適用される場合もあります。
絶対高さの制限
絶対高さの制限は、特定の地域でだけ建物の高さが適用されるものです。
適用地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住宅地域となります。
これらの地域では、原則建物の高さが10mまたは12mのうち、都市計画で決められた高さ制限を超えられません。
建物の外壁、またこれに代わる柱の面と敷地の境界線の間に都市計画で決められた後退距離の確保も必要です。
これは、低層住居環境の保護が目的ですが、例外として周辺に広い公園があり、低層住宅に係る環境が良好な場合は許可される可能性があります。
高度地区の制限
高度地区の制限は、建てられる建物の高さが制限されている地域のことです。
都市計画法によって、用途地域内において市街地の環境を維持して土地利用を増進するため、建物の高さの最高限度もしくは最低限度を設ける地域となります。
高度地区は、制限内容が自治体で変わってくるだけでなく、多くの場合で高さ制限と北側に斜線制限が設けられていることが多いです。
最高限度の高さを決める「最高限度高度地区」、最低限度の高さを決める「最低限度高度地区」があり、後者はオフィス街や商業地に多く見られます。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
建ぺい率・容積率を守って快適な空間を作り出すコツとは

建物を建てる際には、建ぺい率や容積率をチェックしながら建てるようにしましょう。
しかし、自分の家に何が合うのか、どんな内容にしていくのか悩むことも多いでしょう。
そこで、建ぺい率・容積率を守りながら快適な空間にするためのコツをご紹介していきます。
ベランダやバルコニーを設置する
ベランダやバルコニーなど、壁のから突起した部分は長さによって建築面積に含まれないケースがあります。
突起部分の幅が1m以下であれば、建築面積に含む必要がないので、建ぺい率・容積率を守った快適な空間となるでしょう。
1mという幅は決して広くはありませんが、洗濯物などを干す際には適した環境です。
一面だけベランダにするだけで、部屋の印象も開放的に感じられるだけでなく、外からの採光を取り入れることも可能でしょう。
もしベランダやバルコニーを検討しているものの、1mという範囲に狭さを感じる場合は超えることもできます。
幅2m以下の場合は延床面積に含めない選択もできますし、2mを超えた場合は超えた部分だけを延床面積に含めます。
これはベランダやバルコニーに限らず、ポーチ、外廊下、外階段などでも同様の計算です。
そのため、外壁よりも外側に設ける場合は幅に注意しましょう。
ロフトを作る
ロフトは、構造によって延床面積に含まれるかどうかが決まります。
それは、一定の条件を満たした場合は小屋裏の物置という位置になるからです。
小屋裏物置になる条件は、以下のとおりです。
・天井の高さが1.4m以下
・はしごが固定されていない
・ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満である
・ロフト内部に電話、テレビ、インターネットジャックがない
・ロフト内部に収納がない
・ロフトの床仕上げに畳、絨毯、タイルカーペットなどになっていない
・これら以外に居住用仕様になっていない
基準となる数値はありますが、このような条件をクリアすればロフトは階にみなされません。
これだけの条件があると、どうしても用途が限られてしまいますが、本棚を設置して書斎にしたり、子どもの遊び場にしたりするなど、アイデアによっては快適な使い方を見出せます。
構造的に複数の部屋を設けられない場合は、ロフトでプライベート空間を確保できるでしょう。
地下室を作る
建物の高さを増すことができない場合は、地下室を検討してみましょう。
地下室は、建ぺい率、容積率などの基準を守れば広くて開放的な空間にできます。
地下室の面積が全床面積の1/3以下に収まる場合は、建築面積や延床面積に含めなくても問題ありません。
ただし、地下室の天井高は地盤面から1m以下で、住宅として利用される建物です。
地下室は窓から光を取り込めないので使い方に注意しなければなりませんが、コレクションなどを一括で収納できるので使い方次第で便利になります。
吹き抜けを作る
建物内に吹き抜けを作ると、床面積を減らすことができます。
設計したものの、どうしても譲れない建物の形や構造がある場合は吹き抜けを検討してみましょう。
吹き抜けで使える床面積は減ってしまいますが、天井が一部高くなるため開放感があり、窓の位置によっては採光を全体に取り入れられます。
おしゃれな雰囲気にもなるので、快適な空間になるでしょう。
車庫やガレージを作る
車庫やガレージを設けたい場合は、建築面積や延床面積に含まれない方法で取り入れましょう。
外壁のない部分が4m以上連続している、柱同士の間が2m以上空いている、天井の高さが2.1m以上であれば車庫やガレージの柱までの1mは建築面積に含まれません。
建物の階数が地階以外で1階に作る必要があります。
建築の延床面積の1/5以内に車庫やガレージを収めれば含まれることもありません。

INA&Associates Inc.は、不動産管理の専門性とIT技術を活かし、賃貸管理を中心とした総合不動産会社です。 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫において、賃貸管理、賃貸仲介、収益不動産の運用サポートをメイン事業として展開しており、オーナー様の資産価値向上を目的とした賃貸管理サービスを提供しています。また、空室対策、賃料査定、入居者対応の最適化に加え、法人社宅の仲介や不動産活用の提案も行っております。 AI技術を活用した精度の高い賃料査定により、市場に即した適正賃料をご提案。 まずは無料の賃料査定をお試しください。
建ぺい率と容積率が基準を超えた場合はどうなる?

決められた建ぺい率と容積率が基準を超えてしまった場合はどうすべきでしょうか?
この場合は違反建物、既存不適格建物のいずれかに該当する可能性があります。
違反建物は建てた時から既に違反している建物で、既存不適格建物は当初は適法だったものが合わなくなった場合に当てはまります。
既存不適格建物となった場合は、住んでいる分には違反になりません。
ただし、違法建物の場合は超えてしまった部分の解体などが求められる場合があります。
是正を求められることもあり、これらの場合はローンを組むこともできず、建て替えが必要になった時に立ち退きなどの可能性も考えられます。
賃貸物件を建てたいと考えている場合は、建ぺい率や容積率を把握してから設計すると希望どおりの建物になりやすいです。
これは、住みやすさ、周辺の環境に適した決まりになっているので、自由な設計を好む場合は建築士などの専門家に相談しながら可能な範囲を知ると良いでしょう。
ただし、自治体によって細かな決まりもあります。
どのような可能性があるかを把握しながら、建物について調べてみましょう。
