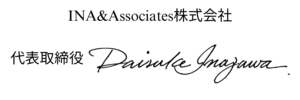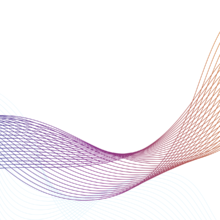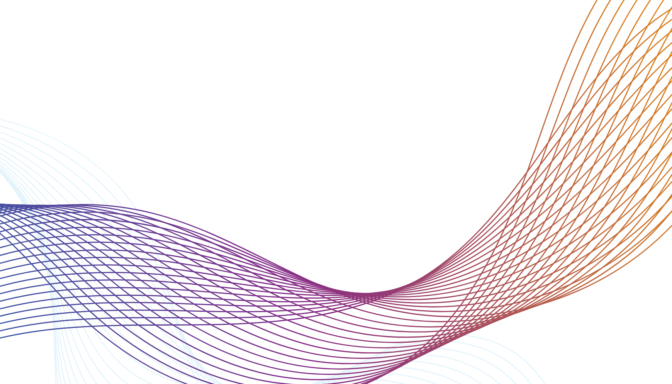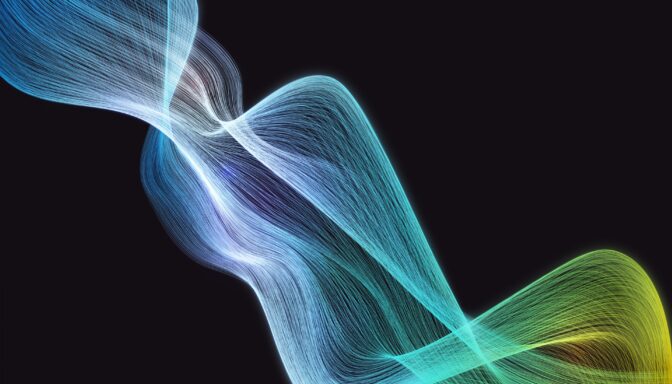成約件数の急増と価格動向 – 金利上昇が促した活況
2025年2月、首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の中古マンション市場は大きな転機を迎えました。成約件数(売買契約の成立件数)が前年同月比+23.9%と急増し、約4年ぶりに月間4,000件超えの水準となりました。この2月の成約件数はコロナ禍後の最盛期だった2021年3月(4,228件)以来の高水準であり、従来ピークだった昨年3月の3,810件も上回っています。成約件数は4ヶ月連続で前年超えを続け、市場の活況が鮮明です。
こうした急増の背景には、日本銀行による追加利上げ決定が大きく影響したと考えられます。筆者は、2025年1月下旬の日銀の政策金利引き上げ(0.25%→0.5%)が売り手・買い手双方の心理に作用し、「金利が上がる前に売りたい・買いたい」というニーズの合致を促したと見ています。実際、4月以降の変動金利上昇が確実視される中で、買い手は将来のローン負担増を避けるため早期購入に踏み切り、売り手も高値かつ低金利のうちに売却しようと市場に出てきました。この金利要因による“駆け込み”が中古マンションのみならず中古戸建てにも及び、2月は中古戸建成約件数も前年比+44.8%という大幅増となっています。つまり、金利環境の転換期に伴う需給の前倒しが、市場を一時的に活性化させたといえるでしょう。
価格面では、成約単価(1㎡あたり成約価格)は首都圏平均で前年同月比+4.8%の上昇となり、こちらも2020年5月以降58ヶ月連続で前年を上回りました。首都圏全体の中古マンション平均成約価格(1戸あたり)も前年同月比+2.6%上昇し、3ヶ月連続で前年超えです。平均価格の上昇率が単価より小さいのは、平均専有面積が前年比▲2.1%縮小しているためで、予算に合わせ以前よりも狭い部屋を選ぶ買主が増えたことを示唆します。実際、2025年1月時点で首都圏全体の成約㎡単価(約81.9万円/㎡)はバブル期だった1990年11月の水準(約80.1万円/㎡)を上回っており、長期にわたる価格高騰が浮き彫りです。2月もこの高値傾向を維持しましたが、一方で前月比では成約単価がわずかに調整局面を迎えています。東日本レインズの18地区別データによれば、2月は18地区中14地区で前月比成約単価がマイナスとなっており、過去半年ほど続いた月次ベースの上昇が小休止した地域が多かったようです。もっとも、前年同月比では依然9地区がプラスで、全体としてまだ前年比では上昇トレンドを保っています。価格の高止まりによる買い控えも見られ始めていますが、低金利下での需給ひっ迫に支えられ、依然として歴史的な高値圏にあると言えます。
新規登録件数と在庫の動向 – 供給不足と売り控えの継続
需要が膨らむ一方で、供給サイドの指標は引き続き伸び悩んでいます。新規登録件数(市場に新規登録された売り物件数)は前年同月比で減少が続いており、2025年1月時点で11ヶ月連続マイナス(同▲6.5%)となっていました。2月についても詳細な公開データは出ていないものの、これまでの傾向から見ると引き続き前年を下回った可能性が高いでしょう。背景には、近年の価格高騰局面で売り控えの動きが続いていたことがあります。すなわち、多くの所有者が「売った後の買い替え先が割高」「現在の低金利住宅ローンを手放したくない」といった理由で売却を先送りし、新規売り出しが細っていたのです。この供給減少トレンドは2024年春頃から顕著化し始め、丸一年以上にわたり市場の売り物件数を押し下げています。
その結果、在庫件数(市場に出ている中古マンション物件の総数)も減少傾向が続き、1月時点で9ヶ月連続の前年割れ(同▲4.2%)となっていました。在庫の絶対数は2024年を通じて減少し続けており、需給は依然として売り手優位のタイトな状態です。実際、2月に成約件数が急増したことで在庫消化が進み、在庫件数はさらに低下した可能性があります。買い手にとっては選択肢が限られる状況が続いており、この供給制約が価格を下支えする要因にもなっています。
もっとも2月は前述のように一部売り手が金利上昇前に売却に踏み切ったため、新規登録の落ち込み幅は若干ながら縮小した可能性があります。実需層の購入意欲が高まる中で、様子見だった売り手がようやく市場に出てきたケースも考えられます。ただし根本的な供給不足はすぐには解消しないでしょう。市場全体の在庫水準が低いままでは、「物件が出れば即売れる」という状態が続き、価格下支え要因となります。実際、2月末時点でもレインズの在庫件数は前年より明確に少なく、需給逼迫は継続中とみられます。このように需給両面の力学として、需要面では金利要因の後押し、供給面では売り控え縮小の兆しがありつつも慢性的な供給不足という状況です。結果として、中古マンション市況は数量的にも価格的にも熱を帯びた2月となりました。今後、金利上昇が本格化する中で需要の勢いがどう変化するか、また春以降に売り出し物件が増えるかどうかが注目されます。
地域別の市況トレンド – 中心部と郊外で明暗分かれる動き

中古マンション市況を地域別に見ると、首都圏内でもエリアごとに温度差が見えてきます。以下の図表は、首都圏を8つのエリア(東京23区・東京都下(多摩地域)・横浜市/川崎市・神奈川県その他・さいたま市・埼玉県その他・千葉県西部・千葉県その他)に分け、それぞれの平均価格・㎡単価・平均専有面積を示したものです。これを見ると、例えば東京都23区の平均価格(約6,290万円)は千葉県(その他地域)の平均価格(約2,061万円)の3倍にも達し、都心と郊外で大きな価格差があることがわかります。都心部では限られた富裕層・高所得層が購入を支える一方、郊外では手頃な価格帯の物件に実需が集中する構図です。2月の市場動向も、このエリア間格差を背景とした明暗が鮮明になりました。
まず東京都心部ですが、価格上昇が続く一方で取引動向にはやや陰りも見られます。23区全体の成約件数は2月も前年比増を維持したものの、その内訳を見ると特に高額物件の集中する「都心3区」(千代田区・中央区・港区)では前年割れが続いているとの指摘があります。実際、住まいサーフィンの分析でも「中古マンション成約件数はやや回復傾向にあるが、都心3区は前年同期を下回り続けている。価格高騰により購入できる層が限られてきていると考えられる」とされています。これは、都心コアエリアの物件価格があまりに上昇したため、買い手層が富裕層や一部投資家に絞られ、取引数の伸びが頭打ちになりつつある状況を示唆します。実際、東京23区の平均価格は2024年後半から月次で2%以上のペースで上昇を続けており、2025年2月時点で直近半年間だけで15%以上も値上がりした計算になります。この急騰に対し、都心部では買い控えが生じやすく、結果的に成約件数の伸びが鈍化していると解釈できます。
しかし一方で、都心部の物件は国内外からの需要の厚みもあり、価格自体は依然強含んでいます。東京都区部の成約㎡単価は2020年から一貫して前年比プラスを維持し続けています。また近年は円安を背景にした海外投資家の購入も都心部で顕著です。実際、この5年間で円に対し中国元は約35%、シンガポールドルは約30%も上昇しており、外国人にとって東京の不動産は割安感が増しました。その影響か「近年、都心部で外国人投資家のマンション購入が顕著」との指摘もあります。例えば港区や渋谷区のタワーマンションには海外マネーが流入し、高額帯でも取引が成立するケースが散見されます。こうしたグローバル需要が都心プレミアムエリアの価格を下支えしており、成約件数こそ伸び悩むものの価格面では強い支持が入っている状況です。
次に城南・城西・城東・城北など都内周辺部や近郊都市の動きを見ると、都心とは異なるトレンドが浮かび上がります。東京23区の周辺エリア(城東・城南・城西・城北)や東京都下(多摩地域)では、2月の成約件数が総じて前年を上回り、2ケタ増の地域もみられました。価格高騰した都心を避け、より手頃なエリアに購買意欲がシフトしている構図です。例えば埼玉県では、さいたま市を中心に取引件数が旺盛で、1月には前年同期比20%以上の増加となりました。2月も同様に好調が続いたと推測され、郊外ベッドタウンでの需要回復が鮮明です。ただし価格面では、埼玉県(特に大宮や浦和など人気エリア以外)では前年割れが続いています。埼玉県全体の成約㎡単価はここ半年ほど微減傾向で、2月も前年比マイナス圏だった模様です。これは、前年度に郊外物件の価格が一時的に上昇し過ぎた反動とも考えられ、価格の頭打ち感が出ている地域もあるようです。
千葉県も似た動きですが、地域によって差があります。千葉県西部(船橋・市川・浦安など東京寄りのエリア)では取引は活発ながら価格は前年を下回る月が続いています。一方、千葉市を含むそれ以外のエリアでは、平均価格がむしろ持ち直しつつあります(例えば千葉市含む「千葉県その他」の平均価格は直近上昇に転じています)。千葉県全体では成約件数が2023年11月以来16ヶ月連続で前年を上回るという好調が続いており、特に価格帯が手頃な郊外・地方都市部で需要が底堅いようです。例えば千葉市では都心へのアクセスと比較的割安な価格からファミリー層の取得需要が堅調で、在庫減少も相まって市況が引き締まっています。また湘南地区(神奈川沿岸部)も注目エリアです。湘南エリア(鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市など)ではコロナ禍以降「郊外移住」「リモートワークによる海沿い人気」の追い風で価格が上昇した経緯があります。直近ではその熱も一服しつつありますが、中古マンションでも海が見える物件やリゾート性の高い物件には根強い引合いがあります。2月の統計でも湘南エリアを含む「神奈川県その他」の成約件数は前年から大きく増加しましたが、成約㎡単価は前年比▲7~8%と下落しており、これは高値圏だった湘南物件の調整が進んだ可能性があります。逆に横浜市・川崎市など神奈川の都市部は、成約㎡単価が前年比+数%と上昇を維持し、2月も取引件数・価格ともに堅調でした。横浜・川崎では都心通勤可能な大規模マンションの需要が強く、価格上昇が一服した現在でも前年を上回る取引水準が続いています。総じて、「都心部は高値維持も取引伸び悩み、郊外は取引活発も価格は横ばい~一部下落」という構図が2月時点で表れています。この傾向は今後の金利環境・経済状況によって一段と鮮明になる可能性がありますが、首都圏という広域で見れば、依然どの地域も需要自体は底堅く、極端な下落や不振に陥っている地域はありません。各エリアの特性に応じた緩やかな調整と成長が混在するのが現状と言えるでしょう。
オフィス市況と再開発の視点 – 都市再編の行方と不動産市場への影響
中古マンション市場と併せて押さえておきたいのが都心オフィス市況や再開発動向です。不動産市場はオフィス需要・都市開発とも密接に関連しており、その変化が住宅市場にも波及し得るためです。まず都心オフィスの空室率の現状ですが、2025年2月時点で東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)の大型ビル空室率は3.58%と、前月比+0.22ポイント上昇しました。これは半年ぶりの空室率悪化となり、新築ビルの竣工(空室を抱えて完成)が要因です。一方、潜在空室率(募集に出ている床面積ベースの空室率)は5.59%へ上昇しており、今後テナント退去予定のスペース等を含めると実質的な余剰感はもう少し大きい状況です。それでも空室率そのものは依然3~4%台で、国際的に見れば低水準を保っています。足元ではオフィス需要も底堅く、2月は新規のテナント契約成立も順調だったため、空室増は限定的でした。テナントの解約より入居の方が多く、都心5区全体で見ると空室面積はむしろ前月から減少しています。従って、現在の都心オフィス市況は「緩やかに需給緩和しつつも、まだ大きな緩みには至っていない」段階といえます。
しかし、中長期的な視点では都心オフィス市場は転換期に差し掛かかっています。特に注目すべきは2025年前後の大量供給です。東京では近年進められてきた超大型再開発プロジェクトが2025年にかけて相次ぎ完成・供給される予定で、それに伴い空室率が6%台後半まで上昇する可能性が指摘されています。民間予測では「2025年、東京で超大型開発が集中し空室率が6.7%まで上昇する」との見通しがあり、これが現実化すれば賃料に下押し圧力がかかるのは避けられません。実際、リモートワーク定着など構造変化も相まって、一部企業はオフィス縮小を進めています。都心部では築古ビルから最新鋭ビルへのオフィス需要の二極化も進行しており、築年が古く汎用性の低いビルではテナント誘致が困難になる例も出てきました。オフィス空間への需要が質的に変わる中、新規供給の増大は市場にゆとりを生み出し、空室率5%超というテナント優位の水準へ移行する可能性があります。このようにオフィス市況は今後「調整局面」に入る可能性があり、都市の不動産全般に影響を与えうるでしょう。
都市の再開発動向にも変化の兆しが出ています。近年の建設費高騰や経済環境の変化により、計画の見直しや延期が相次いでいるのです。象徴的なのが中野サンプラザの再開発計画白紙化です。50年の歴史を持つ中野サンプラザ建替えは、野村不動産等による高さ262mの超高層複合ビル計画が進んでいましたが、事業費の高騰(当初1,810億円→2024年1月に2,639億円、その後さらに+900億円見込みと 当初計画の約2倍)を受け、2024年末から計画変更案の協議が難航。そして2025年3月11日、ついに中野区が最新の計画案を「認めない」方針を発表し、事実上計画は白紙撤回となりました。中野サンプラザ再開発の停止は都心の再開発機運に冷や水を浴びせた格好で、不動産業界にも大きな衝撃を与えています。同様に、五反田の老朽オフィスビル「TOCビル」建替え計画も建築費高騰によりストップし、「2024年問題」(働き方改革関連法による職人不足・コスト増問題)の影響も相まって業界内で波紋を広げています。さらに北区の公共施設「北とぴあ」の建替え構想など、都内各地で予定されていた大型プロジェクトが見直しや頓挫に追い込まれるケースが増えています。
これらは一時的な景気循環の問題のみならず、東京の都市再編の方向性を占う重要なサインといえます。2010年代初頭、東京都は「アジアヘッドクォーター特区構想」を掲げ、大胆な規制緩和や税制優遇で外国企業の誘致を目指しました。新宿・渋谷・品川・大手町・豊洲など都心部の再開発エリアが特区に指定され、数多くの超高層オフィスビルが建設される契機となりました。この政策は一定の成果を上げ、東京は国際業務拠点としてのインフラを充実させてきました。しかし2020年代に入り、コロナ禍でのリモートワーク普及や人口動態の変化により、オフィス需要の構造変化が起きています。大量供給を控える今、当初想定したほどには外国企業が集積せず国内需要も伸び悩めば、新築オフィスの一部は余剰となりかねません。こうした状況下で東京都は「国際金融都市構想」等を打ち出し引き続き海外資本を呼び込もうとしていますが、都市間競争は激しく、簡単ではないでしょう。
もっとも、再開発中止が相次ぐこと自体が供給調整の役割を果たす側面もあります。中野サンプラザや五反田TOCといった計画が延期・中止になれば、その分将来の新規供給は減少し、オフィス市況の緩和圧力もいくらか和らぐでしょう。加えて、既存ストックの利活用という観点では、余剰オフィスを住宅や他用途へコンバージョン(用途転換)する動きも今後本格化する可能性があります。東京都も空室の目立つオフィスビルを住宅やホテルに改装する際の規制緩和を検討しており、欧米主要都市で進む「ダウンタウンの再住宅地化」の流れに沿った都市再編が議論され始めています。老朽ビルの建替えが困難であれば、用途変更による有効活用で街の空洞化を防ぎつつ、新たな需要を創出することが求められるでしょう。
以上を踏まえると、今後の都市再編・ビル需給の方向性としては、「新築偏重からストック活用へ」のシフトがキーワードとなりそうです。首都圏では住宅・オフィスとも新規供給がピークアウトしつつあり、既存物件のリノベーションや用途転換による価値向上が重要度を増すでしょう。それに伴い、不動産市場も「本当に価値のある物件」が選別される時代に入ります。中古マンション市場でも、立地や建物の質によって価格動向に差が開く可能性があります。たとえば都心の築古マンションでも立地が良く将来的に建替えや再開発の余地がある物件は資産価値を保ちやすい一方、そうでない物件は高値是正が進むかもしれません。一方で郊外エリアでも、テレワーク普及に対応した住環境の良さ(広さや自然環境)に注目が集まれば、新たな人気エリアが生まれる可能性があります。都市の構造変化に即した需給バランスの再編が、不動産の価値にダイレクトに影響する時代となってきています。
おわりに:投資・購入検討者への示唆
2025年2月の首都圏中古マンション市場は、金利政策の変化をきっかけに大きく動きました。成約件数が急増し、価格も高止まりする中で、市場の熱気と一抹の不安定さが同居しています。地域別に見れば、都心部では取引量の伸び悩みが見える一方で、郊外では堅調な需要が支えとなっています。これはまさに「価格の都心、量の郊外」という状況で、不動産購入・投資を検討する皆様にとっても戦略が分かれるところでしょう。資産価値の安定を重視するならば依然として都心・駅近・高品質の物件が強いですが、値上がり余地や利回りを狙うならば今後伸びそうな郊外エリアに目を向けるのも一案です。
加えて、オフィス市況や都市開発の動向にもアンテナを張っておくことをお勧めします。都市経済の活力が維持されるか、新たな再開発で街の魅力が向上するかといった点は、住宅市場にも間接的に効いてきます。オフィスの空室率上昇は土地・不動産価格全体の天井を抑える可能性がありますし、再開発中止は周辺エリアの将来価値に影響を与えるでしょう。例えば、中野サンプラザの再開発中止は中野エリアのイメージに影響を及ぼし、中野駅周辺マンションの評価にも何らかの形で織り込まれるかもしれません。一方、品川や八重洲などで進む巨大プロジェクトの完成は、その周辺の居住人気や賃料相場を押し上げることが期待されます。このように不動産市場はマクロ経済・都市政策と連動しますので、広い視点で情報収集することが重要です。
最後に、現在の市場は売り手有利とはいえ金利上昇という新たな要素が加わり始めています。住宅ローン金利が上がれば買主の予算は圧迫されますが、その分価格交渉の余地が生まれる場面も増えるでしょう。実際、直近では都心部以外でわずかながら価格調整の兆しも見られます。購入検討者におかれては、周辺相場や将来の金利動向を注視しつつ、「適正価格かどうか」を見極める目を養うことが肝要です。幸い、中古マンション市場は新築と比べ実勢に即した価格が形成されやすく、情報も豊富に公開されています。信頼できるデータや専門家の知見を活用しながら、ぜひ賢い不動産購入・投資判断をしていただければと思います。首都圏の不動産市場は長期的に見れば依然ポテンシャルの高い市場です。その大きな潮流を踏まえつつ、タイミングと場所を見極めたアプローチで、ご自身にとって有益な資産形成を実現されることを願っております。