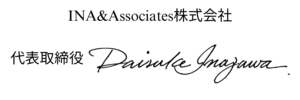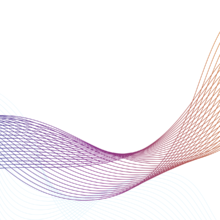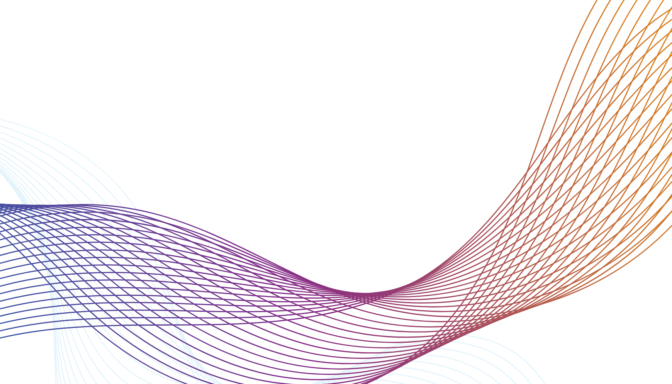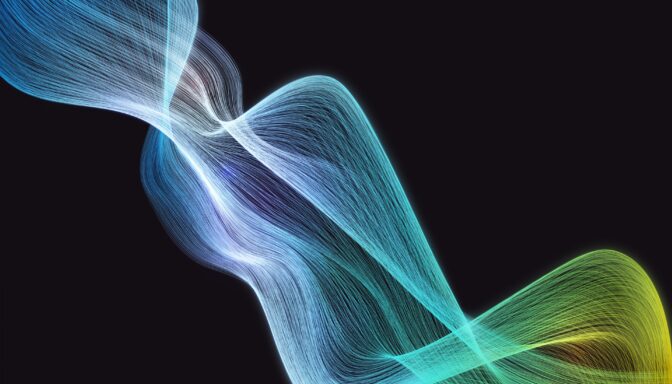経営環境が急激に変化する現代において、企業経営者には長期的視野に立った持続的成長と短期的成果との両立が求められています。私たちINAも、「世界No.1の人財投資カンパニー」を目指し、日々経営に挑戦しています。本稿では、経営の根幹となる理念やビジョンの重要性から、人財(人的資本)への投資、組織文化の構築、人材育成の具体策、短期利益と長期持続性のバランス、失敗と挑戦の価値、そして誠実さと共感を軸にしたリーダーシップまで、経営者・ビジネスパーソンの皆様に向けて包括的に考察します。
理念経営とビジョンの重要性
企業の存在意義や使命を示す経営理念や、将来のありたい姿を描くビジョンは、組織の羅針盤です。理念経営とは、経営理念を経営の中心に据え、あらゆる意思決定や行動をその理念に照らし合わせて行う経営手法を指します。明確な理念とビジョンが定まっている企業では、経営判断に一貫性が生まれ、社員一人ひとりが自発的な指針を持って行動できます。ビジョンが共有されれば部署や職位を超えて方向性が統一され、社員は自分の役割と存在意義を理解して高いモチベーションで仕事に取り組むでしょう。さらに、社外に対しても企業の方向性を示すことになり、明確なビジョンを掲げる企業はブランド価値の向上につながります。実際、経営ビジョンに共感できる企業には優秀な人材が集まりやすく、入社後のミスマッチが減るため離職率の低下にも寄与します。
私自身、経営において短期的な利益追求だけでは企業は本質的な成長ができないと考えています。企業の本質は、明確なビジョンのもと関わるすべての方々が幸福になる持続可能な成長を目指すことであり、そのために重要なのが理念の浸透です。例えばアウトドア用品ブランドのパタゴニアでは、創業者イヴォン・シュイナード氏が環境保護と社会的使命という強い信念を掲げ、単に利益を追求するだけでなく従業員や社会への共感を貫きました。その結果、環境に配慮した製品と社会的取り組みが高く評価され、顧客から強い忠誠を得るなどブランドの持続的成功につながっています。このように理念とビジョンが組織にもたらす力は大きく、経営者はまず自社の存在意義と目指す未来像を明文化し示すことが肝要です。それが社内外の信頼を築き、荒波の時代における不動の羅針盤となります。
人的資本(人財)への投資の意義と方法
企業にとって最も重要な資産は「人」であると私は確信しています。当社では人材を「人財」と記し、かけがえのない財産として位置づけています。近年注目される人的資本経営とは、「人材を資本と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営」だと定義されています。社員一人ひとりの知識・経験・創造力を高めることが、長期的に見て企業の競争力とブランド価値を高めるからです。
人的資本への投資には具体的に採用・教育訓練・待遇改善など様々な方法がありますが、その意義はデータからも明らかです。例えば、ハーバード・ロー・スクールの研究によれば、従業員へのトレーニング(人的資本の蓄積)と財務成果の関係を分析した36本の論文中22本で、教育投資が業績向上に正の相関を持つことが確認されています。トレーニングによって社員の知識やスキルが向上し生産性やサービス品質が高まれば、最終的に売上や利益の向上につながり得るということです。さらに人的資本情報の開示が進む英国企業の研究では、人材育成への投資額当たりの利益が約2.6倍、営業利益率も33%高いとの結果が報告されています。これらは「人への投資」が企業価値を高める有力な証左でしょう。私たちINAでも、優秀な人財の採用と育成に経営資源を集中投下しています。社員が能力を発揮し成長することが組織全体の活力と業績向上の原動力になると信じているからです。
人的資本への投資方法としては、まず公正で魅力的な処遇によって人財を惹きつけ、エンゲージメントを高めることが重要です。給与・福利厚生といった報酬面の充実はもちろん、働きがいのある職場づくりや明確なキャリアパス提示も投資の一環です。また、教育訓練への投資も欠かせません。研修制度や資格取得支援、社外セミナー受講補助などを設け、社員が自己研鑽できる機会を提供することは、将来の企業価値への投資そのものです。当社では定期的なキャリア面談やメンター制度、必要に応じた社外研修の受講支援などを行い、社員の成長を全面的にバックアップしています。さらに、人材データの活用や目標管理制度によって一人ひとりの成長を見える化し、適材適所の配置やスキル開発計画に活かすことも効果的です。人的資本への投資は即効性のある施策ではないかもしれませんが、中長期的には必ずや企業に大きな果実をもたらすでしょう。
チームビルディングと組織文化形成
いくら優秀な人財を揃えても、チームとして力を発揮できるかどうかで成果は大きく変わります。そこで鍵となるのが、信頼と協働に満ちた組織文化づくりと効果的なチームビルディングです。私は常々「人が最大の資産」であると同時に、「人と人の関係性こそが価値創造の源泉」だと感じています。特に不動産業のように人間同士の信頼関係が成果を左右する業界では、チームワークと文化が競争力そのものと言っても過言ではありません。
まず、強いチームを作るには明確な目標の共有と役割分担が重要です。チーム全員が同じビジョンに向かい、自分の果たすべき役割を理解している組織はブレがありません。加えて、信頼関係の醸成が土台となります。メンバーがお互いを信頼し、率直に意見交換できる雰囲気があってこそ、問題解決に向けて知恵を絞り合うことができます。近年注目される心理的安全性の高い職場では、メンバーが失敗を恐れずに発言・挑戦でき、生産性や創造性が向上することが報告されています。Googleの調査プロジェクト「アリストテレス」でも、生産性の高いチームの共通点は他でもなく心理的安全性だったとされます。私たちINAも、安心して意見を述べ挑戦できるオープンで風通しの良い文化を醸成するよう努めています。上下の垣根を低くし、誰もが建設的に意見できる場を作ることで、組織の知恵を最大化できると考えるからです。
組織文化形成には経営トップの姿勢も影響します。経営理念やバリューを社内に浸透させ、それに沿った行動を評価・称賛することが文化を形作ります。例えば当社では、「常に当事者意識を持つ」「明確化・構造化・一貫性・客観性」「自主探求・進取果敢・改過自新」などのバリューを掲げています。これらの価値観に沿った行動を表彰したり、日々の朝礼で社員同士が社訓を唱和したりすることで、理念が単なるお題目ではなく日常の判断基準として根づくよう取り組んでいます。そうした共通の価値観を持つ組織は結束力が高く、困難に直面してもブレずに乗り越えられるのです。さらに、チームビルディング研修や社内レクリエーションも有効でしょう。異部署交流やプロジェクト活動を通じて互いの人柄や強みを理解し合うことで、「この仲間のために頑張ろう」という相互扶助の精神が芽生えます。強い文化とチームは一朝一夕には作れませんが、経営者自らが旗振り役となって理想の組織像を示し続けることで、着実に醸成されていくと実感しています。
人材育成と教育の具体策
人材育成は経営者にとって終わりのないテーマです。私たちの企業理念にも「人財の成長こそが企業の価値を生み出す」とある通り、社員の成長なくして企業の発展はありえません。では、現実にどのような施策で人材育成を進めていくべきでしょうか。ここでは効果的な育成のための具体策をいくつか紹介します。
まず基本となるのは育成制度の整備です。計画的に人材を育てるには、制度や仕組みを用意し、継続的に実践することが不可欠です。代表的なものとして、OJT制度(オン・ザ・ジョブ・トレーニング:現場で先輩が指導)、研修制度(階層別・職能別研修など)、ジョブローテーション制度(部署異動を通じた経験多様化)、人事評価制度(目標管理とフィードバック)、目標管理制度(MBOによる目標設定とレビュー)、メンター制度(先輩社員が後輩をサポート)等が挙げられます。これらの制度を組み合わせることで、人材育成のPDCAサイクルを組織的に回すことができます。例えば新人研修で基礎を教え、OJTで実務スキルを磨き、メンターが適宜相談に乗り、定期評価で成長度合いを確認して次の目標につなげる、といった流れです。
次に教育コンテンツと手法です。単に制度を設けても中身が乏しければ成果は出ません。技術や商品知識の習得はもちろん、リーダーシップ研修やマーケティング研修など将来を見据えた教育も必要でしょう。社内講師による研修に加え、外部機関のセミナー受講やeラーニングも活用できます。最近ではオンライン学習プラットフォームも充実しており、社員が自主的に学べる環境を提供する企業も増えています。また、キャリアパス面談を定期的に行い、各人の目標や希望、適性を把握しておくことも有効です。当社でも上長との1on1ミーティングやキャリア面談制度を導入し、社員のキャリア目標と会社の成長をどう擦り合わせるかを常に対話しています。さらに、実践を通じた成長機会も大切にしています。意欲ある社員には新規プロジェクトを任せたり、小さくともリーダー経験を積ませたりすることで、挑戦の中で学ぶ機会を提供します。人は実践の中でこそ大きく成長するものです。私自身も若い頃に上司から大きなプロジェクトを任された経験があり、失敗のプレッシャーを感じながらも必死でやり遂げたことで飛躍的に成長できました。その経験があるからこそ、今度は私が適度な挑戦機会を与えるよう心掛けています。
最後にフォローと評価です。育成は育てっぱなしでは効果が定着しません。研修後のフォローアップ面談や、習得したスキルを現場で実践するためのサポート体制を整えましょう。上司が日常的にコーチングやフィードバックを行い、学んだことが業務に活かされているか確認することが重要です。また、人材育成の成果を適切に評価・昇進に反映させることも、社員の成長意欲を高めます。「学んでも評価されない」「成長しても処遇が変わらない」ではモチベーションが続きません。社員の努力と成長を正当に評価し報いる文化を作ることも、広い意味での人材育成策と言えるでしょう。以上のように制度・教育内容・フォロー体制を整え、人を育てる風土を醸成することが、強い組織を作る土台となります。
短期利益と長期的持続性のバランス
経営者には四半期ごとの業績目標を達成する責務がありますが、同時にその先の5年10年といった長期の持続的成長も見据えなければなりません。短期と長期のジレンマに悩むマネジメント層は多いでしょう。私も日々、目前の数字を追いながら将来の投資とのバランスに頭を悩ませます。しかし明確に言えるのは、短期利益の最大化だけに囚われていては、いずれ企業は持続的成長の機会を失うということです。
実際、長期志向の経営が成果を生むことは証明されています。マッキンゼーが米国上場企業600社超を15年間分析した研究では、長期的視野で成長戦略を考えるCEOが率いる企業は、平均的な企業に比べて47%も売上が多く、利益も36%高かったと報告されています。にもかかわらず、長期志向の企業は全体の5%未満しかなかったともいいます。多くの企業が四半期ごとの短期目標にどうしても傾注してしまう現状が浮き彫りになっています。しかし幸いなことに、近年はSDGs(持続可能な開発目標)やESG投資への関心の高まりにより、長期的な企業価値創造に重きを置く経営が見直されつつあります。短期的利益ばかりを追求する企業は、顧客や投資家から「将来性がない」「社会に貢献していない」と見なされ、選ばれなくなる時代です。
では実務上、短期と長期をどう両立すべきでしょうか。私はまず経営者自身が長期ビジョンを明確に持つことが出発点だと考えます。長期ビジョンに照らして、短期的な目標達成が将来どう繋がるかを社内に説明し、共感を得ることです。例えば「今期は利益を上げるため経費削減するが、それは○年後の新規事業投資に備えるためである」といった文脈を共有すれば、社員も目先の数字だけでなく未来の目的意識を持って努力できます。また、KPIの設定にも工夫が必要です。短期KPI(売上・利益等)と並行して長期KPI(顧客満足度向上、人財育成度合い、新規事業育成状況など)を設定し、バランスよく評価・管理するのです。そうすることで経営陣も社員も長期的視座を失わずに済みます。さらに、短期の利益が出た時こそ未来への投資に振り向ける決断力が求められます。景気が良い時に蓄えた内部留保を、人材育成や研究開発、ITシステム導入など将来の成長基盤に投じるのです。日本企業は欧米に比べ内部留保が厚いと言われますが、ため込むだけでは社会からの視線も厳しくなりますし、宝の持ち腐れです。勇気を持って攻めの投資に使い、長期的な競争力強化につなげるべきでしょう。
重要なのは、短期と長期を対立するものと考えず、短期の積み重ねが長期を形作るという視点です。今日・明日の積み重ねが会社の未来を創る以上、目の前の業績責任から逃げるわけにはいきません。ただし常に「この施策は将来の何に資するのか?」と自問し、長期ビジョンに沿った短期目標の達成を目指すことが肝要です。経営者として、短期の波に飲まれず長期の舵取りを見失わないよう、常に高い視座で経営を俯瞰していきたいと考えています。
マネジメントにおける失敗と挑戦の価値
経営の道には成功だけでなく必ず失敗がつきものです。しかし私は、失敗は決して恥ずべきものでも、避けるべきものでもないと考えています。むしろ挑戦の証であり、次の成功への貴重な糧です。マネジメントにおいて失敗とどう向き合うかは、組織の成長力を左右する重要なポイントでしょう。
ドラッカーも述べているように「成果を上げるには、失敗を恐れず大胆に挑戦すること」が必要です。挑戦しない、部下に挑戦させない環境から生まれるのは組織の衰退のみだ、とある経営者は語っています。全員が安定志向で現状維持しかしない会社にイノベーションは起こりません。私自身、不動産業界の旧態依然とした商習慣に疑問を感じ、誰も手掛けていなかったITと不動産の融合に挑戦したからこそ、今のINAがあると自負しています。当然その過程では数多くの失敗も経験しました。しかしそれらの挑戦と失敗から得た洞察が、今日の事業モデルやサービス改善に生きています。「失敗から学ぶ」という文化なくして、企業が進化し続けることはできないでしょう。
大切なのは、組織として失敗を許容し学びに変える仕組みを持つことです。まず経営者自らが「チャレンジした結果の失敗」は責めない姿勢を明確に打ち出す必要があります。社員が失敗を隠さず報告できる心理的安全性が確保されれば、そこから問題点を洗い出し次の改善策を講じるPDCAが回ります。当社では「失敗は次への財産」という考えのもと、プロジェクト後に良かった点・悪かった点をチームで振り返る仕組みを設けています。上手くいかなかった事例もオープンに議論し、「なぜ失敗したのか」「次はどうするか」をチーム全員の知恵に変えるのです。そうすることで同じ過ちを繰り返さず、逆に失敗を糧に組織知が蓄積されていきます。また、「ここはチャレンジしてみよう」という計画的リスクテイクの場面を作ることも意識しています。新規サービス開発など、不確実性は高いが成功すれば大きなリターンが見込める領域には、敢えてリソースを割いて挑戦するのです。もちろん闇雲に失敗を推奨するわけではありませんが、「本気の挑戦から得られる失敗」は将来の成功の種であると社員に伝えています。
失敗に寛容な文化を醸成する一方で、無謀な挑戦と計画なき失敗は避けるようにも指導します。単に準備不足や注意不足で起きた失敗は、しっかり反省点を洗い出し再発防止策を講じなければなりません。重要なのは、挑戦と失敗から学習する姿勢です。失敗したらその原因を分析し、必要なら自分を変革するくらいの覚悟で学ぶこと。それを繰り返せば、組織として挑戦力と適応力が飛躍的に向上します。現に、世界的企業の中には「Fail Fast, Fail Forward(素早く失敗し、そこから前進せよ)」を合言葉にイノベーションを起こしている例もあります。日本でも最近はスタートアップ企業を中心に失敗談を共有する文化が広まりつつありますが、これは非常に良い傾向です。経営者は率先して自らの失敗もオープンに語り、部下に安心して挑戦してもらう雰囲気を作りたいものです。
誠実さと共感を軸としたリーダーシップ

最後に、経営の要であるリーダーシップについて触れます。組織を率いるリーダーに求められる資質はいくつもありますが、私が特に重視するのが「誠実さ」と「共感力」を軸としたリーダーシップです。高度に情報化された現代、人々はリーダーの本質を敏感に感じ取ります。口先だけのリーダーや信頼できない上司についていこうとは誰も思いません。誠実(インテグリティ)であること、そして相手の立場に立って考える共感を持つこと——これは古今東西、優れたリーダーに共通する要件ではないでしょうか。
まず誠実さ(Integrity)について。誠実なリーダーとは、一貫した倫理観を持ち自らの言行に責任を負う人です。にもあるように、共感型リーダーは約束を守り、一貫した振る舞いで他者からの信頼を築きます。部下を欺いたりごまかしたりしない真摯さが、リーダーとメンバーの間に揺るぎない信頼関係を育むのです。例えば私が尊敬する経営者の一人である稲盛和夫氏(京セラ創業者)は、「人間として何が正しいか」を判断基準に経営判断を下すことを信条とされました。社員との約束や社会への責任を果たす姿勢を貫いた結果、従業員はもとより取引先や社会からも篤い信頼を勝ち得て、京セラという企業の礎を築かれたのです。私自身も、常に正直であること、言ったことはやり抜くことを心掛けています。失敗した時には自分の非を認め、責任を取る覚悟も欠かせません。リーダーが誠実であれば、たとえ困難に直面しても組織は乱れずついてきてくれるものです。
次に共感力(Empathy)です。共感力とは、相手の立場や感情を理解し尊重する力です。ビジネスは人と人との協働ですから、共感なくして円滑なコミュニケーションやチームワークは成立しません。共感力の高いリーダーはメンバーの声に耳を傾け、必要な支援や配慮を行うことで心理的な安心感を提供します。その結果、メンバーは自分が大切にされていると感じ、主体的に力を発揮するようになります。米マイクロソフト社のサティア・ナデラCEOはまさに共感型リーダーシップへの転換を図り、社員の幸福と多様性を重視する文化改革を行いました。その共感に根ざしたアプローチが社員のモチベーションと創造性を高め、マイクロソフトの革新的成長を加速させたことは有名な話です。このケースは、共感に基づくリーダーシップが巨大企業でも大きな成果を生むことを示しています。私も微力ながら見習って、社員一人ひとりの声に耳を傾け、喜びや苦労に寄り添う経営を心掛けています。経営トップ自らが共感の姿勢を示すことで、組織全体に思いやりのカルチャーが浸透し、結果として社内外との強固な信頼関係を築けると考えるからです。
誠実さと共感を軸に据えたリーダーシップは、一見ソフトに映るかもしれません。しかし、それこそが組織の結束と持続的成果を生む強さの源泉です。短期的に見ると、命令や権限に頼ったほうが迅速に結果を出せる場面もあるでしょう。ですが長期的には、信頼と共感に基づく組織は困難に直面したときほど粘り強く、一丸となって乗り越える力を発揮します。共感型リーダーはメンバーの多様な個性を活かし、協力を促進して問題解決に当たらせることができます。また誠実なリーダーは率先垂範によって組織文化を健全に保ち、不正や内紛を未然に防ぎます。まさに「柔よく剛を制す」で、優しさや真摯さといった一見柔らかな資質が、組織を強くするのです。経営者として私も、強い信念と同時に大きな包容力を持ったリーダーでありたいと願っています。
不動産業界における特有のマネジメント課題
最後に、INAが属する不動産業界ならではのマネジメント課題について触れておきます。業界の特性を踏まえた上でマネジメントを行うことは、経営戦略を成功させる上で欠かせません。不動産業界は他の業界に比べ、いくつか特有のチャレンジがあります。
第一に慢性的な人手不足と人材流動性の問題です。不動産仲介業などでは歩合制による給与体系を採用する企業が多く、成績が出せない社員は退職し、優秀な営業ほど条件の良い他社へ移ってしまう傾向があります。一人前になるまでに時間がかかる属人的な業務であるにもかかわらず、人材の定着が難しいのです。このため各社とも人材獲得競争が激しく、採用と育成にかかるコスト負担が大きいという課題があります。また、不動産業は経験知がものを言う部分が多く、ベテラン社員のノウハウをいかに組織に蓄積・継承するかも重要です。世代交代が進まず高齢化する企業では、若手が成長する前にベテランが退職してしまい知見が失われるリスクもあります。こうした状況下で、人材育成と定着は業界全体の喫緊の課題です。当社では人財投資を掲げていることもあり、特に新人の育成にはマンツーマンのOJTや早期戦力化プログラムを用意して、早く一人前に育てると同時に長く働き続けてもらう工夫を凝らしています。具体的には、不動産取引の一連のプロセスを体系的に学べる研修や、若手でも成果を挙げられるようITツールを活用した営業手法の導入、実績だけでなくバリュー体現やチーム貢献も評価する人事制度などを整え、短期的な成果だけで評価される風土と一線を画しています。業界全体が人手不足とはいえ、「人が辞めない会社づくり」「人が成長する業界づくり」に挑むことが、我々の使命だと考えています。
第二にテクノロジーへの適応と信頼性向上です。不動産業界は近年大きな変革期を迎えています。従来は対面営業や紙の契約書が当たり前でしたが、ITの活用が急速に進んでいます。例えばオンラインで重要事項説明を行う「IT重説」や契約書類の電子化、物件のVR内覧、AIを活用した不動産査定といった新しい技術が次々と導入されています。コロナ禍以降は非対面での営業も一般化し、顧客のニーズも変化しました。こうした不動産テックの波に乗り遅れると、業務効率やサービス品質の面で競合に差をつけられてしまいます。一方で、不動産取引は人生における重要な契約でもあり、依然として信頼産業の側面が強い業界です。最新テクノロジーを導入して利便性を上げつつも、「人間によるきめ細かな対応」や「安全・安心への配慮」はなお欠かせません。このバランスを取ることがマネジメントの課題です。具体的には、社内にテクノロジーに明るい人材を確保・育成し、システム導入を推進する一方、顧客対応研修やコンプライアンス教育を強化してサービスの質と信頼性を担保する取り組みが必要です。幸い当社はテクノロジー事業も展開しており、社内にIT人材が多く在籍しています。その強みを活かし、業務のデジタル化とサービス品質向上の両立に努めています。例えば物件提案にAIレコメンドを導入しつつ、最後は担当者が直接お客様にヒアリングして提案内容を微調整する、人と技術のハイブリッド型アプローチを取っています。また、お客様からの信頼を守るために法令遵守や情報セキュリティにも万全を期し、内部統制を強化しています。不動産業界全体でも、テック活用と信頼性向上を如何に両立するかが今後の鍵を握るでしょう。
第三に市場環境の変化への対応です。日本国内では少子高齢化による人口減少や空き家の増加、都市と地方の二極化など、不動産市場を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。不動産業ビジョン2030などでも指摘されるように、旧来型のビジネスモデルだけでは持続的な成長が難しくなっています。このため各社とも新たなビジネス機会を模索しています。例えば不動産の有効活用コンサルティングやリノベーション、海外不動産事業、またはFinTechとの融合など、従来の仲介・管理の枠を超えた展開です。当社も「総合不動産テック企業」として、不動産流通・管理だけでなくコンサルティングや人財紹介など多角的に事業を展開しています。多角化には組織体制の再編や新規事業人材の登用などマネジメント上のチャレンジも伴いますが、市場変化に対応し企業を成長させていくためには避けて通れません。経営者として、市場のトレンドを注視しつつ自社の強みを発揮できる領域に資源を投入し、新陳代謝を促す覚悟が求められます。
以上、不動産業界特有の課題を挙げましたが、裏を返せば課題はチャンスでもあります。人手不足だからこそ人財育成に本腰を入れれば競争優位を築けるし、IT化が遅れているからこそ先んじてDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めれば業界をリードできます。経営者として重要なのは、業界特性を正確に捉え、自社ならではの解決策を示すことです。私は常に「業界の常識を疑い、より良い方法を追求する」姿勢で組織を導いていきたいと思います。
おわりに:人を想い、未来を創る経営へ
マネジメントの本質は、「人を活かし、持続的な未来を創造する」ことにあると信じています。本稿で述べたように、理念とビジョンで組織の軸を定め、人財に投資し、強いチーム文化を育み、長期視点を持ちながら挑戦を奨励し、誠実かつ共感的に人々を率いる——これらは決して華々しい戦略論ではありませんが、経営の土台として極めて重要な要素です。私は経営者として日々試行錯誤の連続ですが、社員たちの成長と笑顔、そしてお客様や社会からの信頼こそが何よりの成果だと感じています。
INAのミッションは「人間的想像力とテクノロジーの融合を通じて、あらゆる人が正当に評価され、報われる社会を創る」ことです。この実現に向け、理念に基づいた経営と人的資本への惜しみない投資を続けていきます。
短期的な波風に一喜一憂することなく、確固たるビジョンを羅針盤に社員とともに航路を進んで参ります。その航路の途中で失敗や困難があっても、必ずやそれを学びに変え、更なる挑戦のエネルギーとします。すべてのステークホルダーの幸福を最大化するというビジョンの下、誠実さと共感を持って人を導き、共に未来を創る経営——それが私の信じるマネジメントの道です。