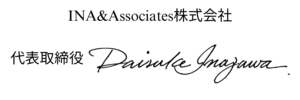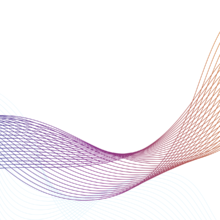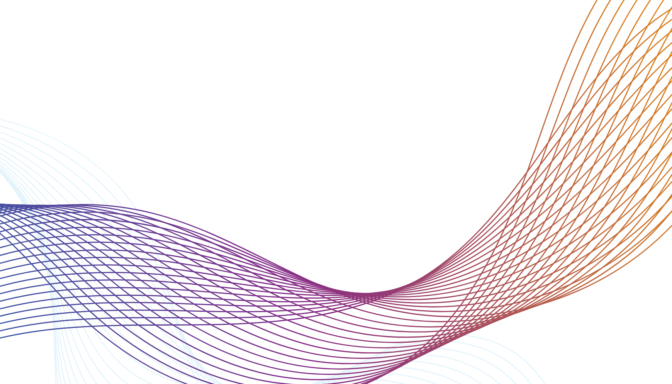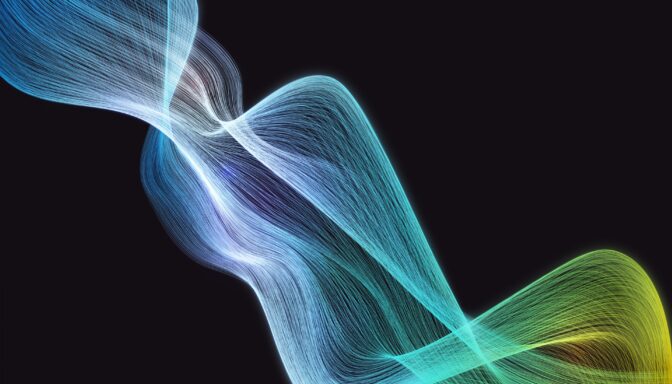私も事業として携わっている不動産仲介管理業務の現場では、近年大きな変化が起きています。従来はお客様に店舗へご来店いただき対面で対応するのが主流でした。しかし、インターネットやIT技術の発展、さらには新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、オンラインでの対応が急速に普及しました。例えば、物件情報の検索から内見予約、重要事項説明(いわゆるIT重説)や契約手続きまでを非対面で完結できる仕組みが整いつつあります。デジタル技術の活用により、書類への押印や紙媒体でのやり取りを省略した電子契約も増えており、サービス提供形態の デジタルシフト が進んでいます。
こうしたデジタル化・オンライン化と並行して、業務の進め方にも変化が見られます。業務のプロセスを複数の担当者で分担する業務の分業化が顕著になってきました。私自身、INAで不動産事業の現場と経営に長年携わってまいりましたが、その経験を踏まえ、本稿では現場業務の変化に組織としてどう対応すべきかについて考察いたします。
現場業務の変化:来店中心からオンライン対応へ、そして分業化
かつて不動産仲介では、お客様が不動産店舗に来店し、担当者が物件紹介から内見同行、契約締結まで一貫して対応するのが一般的でした。現在では 来店中心の営業からオンライン対応への移行 が進み、お客様とのやり取りの多くをメールやウェブ会議システム、電話で完結できるようになっています。お客様自身がポータルサイトで物件情報を収集し、問い合わせを行い、オンライン上で物件の内見動画を視聴したり、ウェブ通話を通じて詳細説明を受けるケースも珍しくありません。加えて、賃貸借契約の電子化が普及し、契約書類の取り交わしもオンラインで完了する事例が増えています。このように現場ではサービス提供の形態が変容し、業務プロセスの見直しと効率化が求められる時代となりました。
こうしたオンライン化の流れに対応する中で、業務の分業化も進んでいます。一人の営業担当者がすべての業務を抱えるのではなく、プロセスごとに役割を分けて専門スタッフが対応する体制です。仲介業務における具体的な分業の例として、次のような担当分野が挙げられます。
- 物件情報の掲載・管理担当:空室物件の情報をオーナーや管理会社から収集し、不動産ポータルサイトや自社ホームページに正確かつ魅力的に掲載する業務を専門に行うスタッフ。
- 反響対応担当:掲載された物件情報を見て問い合わせてきたお客様(=反響顧客)に対し、メールや電話で迅速・丁寧に応対するスタッフ。物件の空室状況確認や条件の簡易ヒアリングを行い、来店や内見のアポイントを設定します。
- 来店・内見対応担当:実際に来店されたお客様への対面接客や、現地での物件案内(内見)を担当する営業スタッフ。お客様のニーズを詳しく伺い、適切な物件提案や契約条件の調整など、対面ならではのサービスを提供します。
- 契約手続き担当:申込後の契約関連業務を処理するスタッフ。重要事項説明書や契約書類の作成、契約締結の手続き、入居までの各種連絡調整を専門に行い、法的手続きや事務処理を正確かつ迅速に進めます。
このようにプロセスごとに役割を分担することで、それぞれの担当者が自分の業務に集中でき、業務効率とサービス品質の向上が期待できます。実際、分業制を導入した企業では、担当者の業務負荷が適正化され、お客様への対応スピードが増すことで成約率向上や売上増加につながった事例が多く報告されています。専門分化によって各領域のスキルが蓄積されるため、顧客満足度の向上にも寄与しているのです。
分業化がもたらす効率化と浮上する課題

業務の分業化には上記のように効率化やサービス向上という大きなメリットがありますが、その一方で組織運営上の課題も浮上します。代表的な懸念の一つが、「分業が進むと人が育たないのではないか」という点です。担当領域を限定しすぎることで、社員一人ひとりが仲介業務の全体像を学ぶ機会を失い、自分の専門外のスキルや知識が身につかないのではないか──という不安です。
例えば、物件情報の入力・掲載ばかり担当していたスタッフが、将来お客様対応にシフトしようとしても、接客の現場経験が乏しければスムーズな対応が難しいかもしれません。同様に反響対応に特化してきたスタッフが新たに契約業務を任された場合、契約書類の作成手順や関連法知識が不足して戸惑う可能性があります。分業制は専門性を深める半面、業務範囲が固定化されることでジェネラリスト(総合的なスキルを持つ人材)の育成が疎かになる恐れがあるのです。
また、役割が細分化されることで各担当者が自分の業務目標の達成には集中できても、組織全体を見渡す視点が育ちにくくなる傾向も指摘できます。極端に言えば、自分の担当範囲外の課題には関与しなくなり、部署ごとの最適化を優先するあまり全体最適を損なうセクショナリズムに陥るリスクも否定できません。こうした人材育成上・組織運営上の課題にどのように対処するかが、分業化を進める上での重要なポイントとなります。
強みを生かした適材適所の人財活用による解決策
では、分業化によるこれら課題に対してどのような対策が有効でしょうか。鍵となるのは、各人の強みを生かした適材適所の人財活用だと私は考えております。分業という戦略自体は業務効率や専門性向上のために有効ですが、それに伴う人材育成の停滞を防ぐには、社員一人ひとりの成長に配慮した運用が不可欠です。
まず、社員を企業の「人財」と位置付け、その成長を会社の将来と結びつけて捉える姿勢が前提となります。適材適所とは、各社員が最も力を発揮できるポジションで活躍してもらうことですが、同時にその人が将来的に新たな力を身につけていけるよう支援することでもあります。現時点で得意な業務に専念してもらいつつ、必要に応じてジョブローテーションや研修を実施して他分野のスキル習得機会を提供することが有効でしょう。
例えば、あるスタッフが顧客対応力に優れコミュニケーションが得意であれば、当初は反響対応や来店接客の担当としてその強みを発揮してもらいます。一方で、本人が希望すれば契約実務に関する研修の機会を与え、中長期的には契約業務にもチャレンジできるように育成します。逆に、事務処理能力が高く正確性を強みとするスタッフには契約手続き担当として専門性を高めてもらいながら、接客スキル向上の研修にも参加させることで将来的に顧客対応もこなせる人財に成長してもらう、といった柔軟な人事運用が考えられます。
このように、強みを生かし弱みを補う人財育成を組み合わせることで、分業化のメリットを享受しつつ「人が育たないのではないか」という懸念に応えることができます。適材適所で配置された人材は高いモチベーションと成果を発揮しやすく、それぞれが専門分野で成長することが組織全体の持続可能な成長にもつながります。分業化と人財育成は対立するものではなく、運用次第で両立・相乗効果を生み出せるのです。
縦の分業:四層のマネジメント構造による組織運営
分業化を成功させ、人財育成と組織全体の成果を両立するためには、現場レベルだけでなくマネジメント層の役割分担も明確にする必要があります。私は組織運営において、横方向の業務分担だけでなく縦方向の指揮系統においても機能分化を図ること、すなわち「縦の分業」を重視しています。INAでは、現場から経営層に至るまで次の4階層を設け、それぞれ異なるミッションを担うマネジメント構造を採用しています。
- 現場責任者(店長・拠点長クラス):各店舗や拠点の最前線で営業活動を統括し、日々の業績責任を負うポジションです。具体的には、スタッフの指導・育成や目標管理、現場で発生する問題の解決などを担い、チームを率いて現場力の最大化に努めます。
- 課長(人財育成担当):複数の現場を束ね、部下の成長と組織力向上に責任を持つ中間管理職です。課長層は現場から上がってくる人財を育てることに主眼を置き、OJT計画の立案や研修実施、評価・フィードバックを通じて社員の能力開発を支援します。分業体制下でも人が育つ風土を作り出す、いわばキーパーソンと言えるでしょう。
- 部長(商品企画・事業開発担当):自社のサービスや商品を磨き上げ、事業戦略に反映させる上級管理職です。仲介業務そのものや関連サービスを「商品」と捉え、市場動向や顧客ニーズを踏まえて新しいサービスモデルや業務プロセスの改革を推進します。現場から寄せられる意見やデータを分析し、提供するサービスの価値向上に努めます。
- 経営層(環境整備・経営戦略担当):社長・役員などトップマネジメント層であり、組織全体が円滑に機能するための環境整備と長期的な経営戦略の策定が使命です。人事制度の構築・運用、財務戦略の立案、マーケティングや広告戦略の決定、ITインフラの導入など企業経営の基盤を整える役割を担います。また、経営理念やビジョンを定め、それを全社に浸透させる 理念の共有 も経営層の重要な責務です。
このように階層ごとに明確な役割分担を設定することで、組織全体として横の分業(現場業務の専門化)と縦の分業(指揮系統の機能分化)が噛み合い、効果を発揮します。現場責任者が最前線で即応的な判断とチーム統率に注力できる一方、課長が将来の担い手となる人材の育成に専念し、部長が事業の方向付けと革新に取り組み、経営層が持続的成長のための環境と戦略を整備する。この 縦のライン がしっかり機能することで、各現場の横の分業体制も軸がぶれずに運営され、組織として 適材適所 の人員配置と能力発揮が体系的に行えるのです。
トップマネジメントの役割と理念の共有
最後に、トップマネジメントの役割について触れておきます。トップである経営層の舵取り如何(いかん)で、組織の成長軌道は大きく左右されます。経営層は人事、財務、営業戦略から企業文化に至るまで、組織運営のあらゆる側面を俯瞰し、全体最適の視点で意思決定を行うことが求められます。創業間もないINAでは、経営者自身が現場に立って営業をこなしながら、人事や経理、集客のための広告企画まで幅広く兼務することもあります。しかし、事業規模が拡大するにつれ、こうした兼務状態を見直し、各分野の専門担当者に権限委譲していくことが重要です。
具体的には、人事部門を整備して採用・評価・教育の仕組みを確立したり、財務責任者を置いて資金繰りや収支管理を専門家に任せたり、マーケティング部署を設けて効果的な集客戦略を立案するなど、組織体制を高度化していきます。トップマネジメント自らも各領域の知見を持ちつつ、最終的には「プレイヤー」ではなく全体を見渡す マネージャー として指揮に徹することが、企業を長期的に伸ばすポイントです。また、トップが明確なビジョンと経営理念を掲げ、それを組織内に徹底して 共有 することが、分業化された組織を一つの目的に向かわせる推進力となります。経営トップによる理念の提示と共有は、社員の価値観と努力の方向性を統一し、組織全体の一体感を生み出す源泉なのです。
おわりに
不動産業界の現場はテクノロジーの進化と社会環境の変化に伴い、大きな転換期を迎えています。来店型からオンライン中心への移行、業務の専門分化(分業化)という流れは今後さらに加速していくでしょう。その中で企業が持続可能な成長を遂げるためには、単に効率を追求するだけでなく、「人財育成」と「適材適所」によって社員一人ひとりの価値を最大限に引き出すことが不可欠です。組織のすべての階層で役割と使命を明確にし、トップが率先して理念を示し共有することで、分業化された組織も一丸となって同じ方向へ進むことができます。現場の力と個々の人財の成長が噛み合ったとき、初めて真の意味で持続可能な発展が実現すると信じております。